 お悩み
お悩み子供が特別支援学校に入学するんだけど、実際はどんな雰囲気なのかな?



就学相談や見学をしたけど、普通級とは違う面も多いだろうし不安……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、息子が特別支援学校に入学して感じたギャップを紹介します。
- 特別支援学校の入学後に感じたギャップ
- 特別支援学校の入学後のギャップを減らす方法
- 特別支援学校の入学後に意識したこと
特別支援学校への入学は、子供にとっても親にとっても生活が大きく変わるはずです。
入学前は、子供に合ったレベルで安心できる環境で学べるはずと期待しつつも、実際に通い始めてから「思っていたのと違う」と感じるギャップに戸惑うことも少なくありません。
私も下調べをした上で、息子を特別支援学校に入学させましたが、先生や子供との距離の近さ、生活に根ざした活動の多さ、準備物や連絡帳の負担など、実際に通わせてみてわかったことがたくさんあります。
本記事では、入学後に感じたギャップや意識したこと、さらにそのギャップを減らすための工夫を体験談とともにご紹介します。
【体験談】特別支援学校の入学後に感じたギャップ
息子が入学するにあたり、就学相談や学校見学、個別の育児相談などで何度か学校には足を運んでいたものの、入学後にはやはり地域の公立小とは違うなと思う機会が何度かありました。
息子が特別支援学校に入学してから感じたギャップは、主に以下の通りです。
- 保護者・児童と教員の距離が近い
- 縦割り活動や障害・特性によるグループ活動が多い
- 生活に根ざした活動が多い
- 療育的なアプローチは少ない
- 子供の意見・気持ちに寄り添ってくれる
- 連絡帳に生活面や子供の様子を書かなければならない
- イレギュラーな持ち物が多い
- 給食が美味しそう
- PTA活動が盛ん
それぞれ詳しく解説していきます。
保護者・児童と教員の距離が近い
特別支援学校に入学して最初に感じたのは、先生と保護者、そして子供との距離感がとても近いということです。
入学前は学校というと、先生にある程度お任せして、家庭と学校は線引きがあるものだと思っていました。



子供たちが通っていた幼稚園がマンモス校で保護者への連絡がほぼない園だったのも大きいかもしれません
しかし実際には、毎日の連絡帳や個人面談、送迎時の会話などを通じて細やかに情報を共有し合う機会が多くありました。



先生方も一人ひとりの子供の状況を深く理解しようとしてくれ、非常に安心できます
縦割り活動や障害・特性によるグループ活動が多い
通常学級では学年ごとやクラスごとの活動が中心ですが、特別支援学校では学年をまたいだ縦割り活動や、障害の特性に応じたグループ活動が多いのも大きな違いでした。
例えば、図工や音楽、体育などの授業では、学年別や障害別などでグループ分けして様々なメンバーで授業を行っています。



指導する先生が変わることもありますし、様々な人と触れ合う良い機会になりそうです
学力や発達段階がバラバラだからこそ、それぞれに合った形で力を伸ばす工夫がなされていると感じます。
生活に根ざした活動が多い
特別支援学校の授業内容で印象的だったのは、生活に直結する学びが非常に多いことです。
買い物学習や調理実習、清掃活動など、日常生活に必要なスキルを習得することに重点が置かれています。



着替えや食事、トイレなど普通学級では指導されずしつけの問題とされることも、保護者と一緒に指導してくれるので助かっています
親としては「もっと学習的な内容はやらないのかな?」と感じる部分もありました。
生活に直結した学習をすることで、学んだことが生活で役立つ機会も増え息子の自身につながっているようです。
療育的なアプローチは少ない
入学前は、「学校でも療育のようなトレーニングをしてくれるのでは」と期待していたのですが、実際には医療や療育的な専門プログラムはそれほど多くありませんでした。
もちろん、ひらがなの読み方や運筆、数字など療育でも学校でも共通して取り組む内容もあります。
しかし、特別支援学校はあくまで教育機関であり、発達支援やリハビリを専門に行う場ではありません。
特別支援学校のカリキュラムは、個別療育よりも下記のようなことに重点を置いている気がします。
- 誰と学ぶか(友達や教職員と一緒に活動することも多い)
- どのように学ぶか
- 学んだことをどのように暮らしに活かすか
授業の中で発達を促す工夫はされていますが、個別療育やリハビリのように机に向かってひとりで課題に取り組む形ではないので、最初は「これで息子は成長するのだろうか……」と不安な気持ちもありました。
今では、学校と療育機関は役割が違うと理解することで納得し、月に一度、専門の個別療育に通うことにしています。



集団生活は放デイ、個別の課題は療育+学校でフォローみたいに外部の機関と連携するようにしています
子供の意見・気持ちに寄り添ってくれる
特別支援学校に入って感じた大きな安心材料のひとつは、先生方が子供の気持ちや意見をとても大切にしてくれることです。
小さなこだわりや特性からくる反応に対しても、頭ごなしに「ダメ」と言うのではなく、子供なりの理由を理解しようとしてくれます。
もちろん、ダメなことはダメと子供に伝えてくれるのですが、伝え方やじゃあどうしたらお互い納得のいく方法で過ごせるかなどを一緒に工夫してくれる点が非常にありがたいと感じます。
私としては集団生活についていけず毎日困りごとを報告されても困るし、反対に野放しにされても心配だと思っていました。
今の子供の意見を尊重した上で正しい方向に導いてくれる先生方には感謝の気持ちしかありません。
連絡帳に生活面や子供の様子を書かなければならない
入学して驚いたのは、連絡帳に書く内容の多さです。
通常の小学校であれば、欠席時や個別の連絡が必要なときのみ連絡帳に記入する形態がほとんどのはずです。
一方、特別支援学校では昨晩の睡眠時間や排便の有無、体調などを毎日書く必要があります。



保護者が報告するのみでなく、先生も毎日給食の食べ具合やトイレの回数、その日の様子などを丁寧に書いてくれます!
子供たちはみんな幼稚園で連絡帳文化に慣れていないこともあり、最初は負担に感じましたが、先生が学校生活の中で子供の行動と家庭での様子を照らし合わせることで、より適切なサポートにつながると感じています。



困りごとの相談や息子が最近ハマっているものなどを共有できて助かっています!
イレギュラーな持ち物が多い
特別支援学校では、通常のランドセルと教科書だけではすまない日が多いのも特徴です。
生活単元学習や調理実習など座学以外の活動も多いため、その都度エプロンや三角巾、軍手、買い物用の小銭などイレギュラーな持ち物の用意が求められます。



「来週エプロンセット持たせてください!」などと直前に言われることもあり、親としては緊張します
給食が美味しそう
特別支援学校は都立扱いだからかどうかはわからないのですが、地域の公立小の給食より量が多くおいしそうだなと思っています。



市区町村より予算が潤沢なのでは?と勝手に思っていました
息子の通う特別支援学校では、品数も3つくらいは常にありますし、季節のフルーツが給食に出ることも多くあります。
PTA活動が盛ん
特別支援学校では、PTA活動が思っていた以上に活発で、大変そうな印象でした。
普通級の小学校に比べると、保護者同士の結びつきが強いのもありますが、PTA活動の重要な業務のひとつとして、自治体などへの陳情があるからです。
障害のある子供の代わりに困りごとを発信して支援を求めたり、他の学校とのつながりを強化したりする点が支援学校のPTA活動の特徴だと感じました。
PTAの役員になると月に何度か都心の方に行かなければならないこともあるし、それ以外でもしょっちゅう集まりがあるらしいと聞いていたので、我が家はPTAには加入しないこととしました。


特別支援学校の入学後のギャップを減らす方法
特別支援学校に子供が入学してからのギャップを少しでも減らしたいのであれば、以下のような対策をしておくことをおすすめします。
- 就学相談・見学で学校をしっかり見ておく
- 入学前の不安は先輩保護者・教員に相談し解消しておく
- 医療機関や療育センターなど学校以外の相談先も作っておく
- SNSで情報収集をしておく
それぞれ詳しく解説していきます。
就学相談・見学で学校をしっかり見ておく
入学後のギャップを少しでも減らしたいのであれば、就学相談や学校見学で学校や児童の様子を見ておくことが何より大切です。
就学相談では、教育委員会や専門スタッフが子供の発達や特性をふまえて学校選びのアドバイスをしてくれたり、学校見学の手配をしてくれたりします。
学校見学や体験入学では、授業の雰囲気や子供たちの様子、先生の関わり方を実際に確認可能です。



パンフレットや説明だけではわからない学校の空気感を感じ取れるので、複数の学校に参加してみることをおすすめします
入学前の不安は先輩保護者・教員に相談し解消しておく
入学前は「学校生活についていけるだろうか」「給食や登下校に不安がある」など、保護者として心配が尽きないものです。
そのような不安を1人で抱えていると煮詰まってしまうので、入学前の面談や説明会で先生に率直に相談してみましょう。



多くの学校や先生は親身になって対応してくれるはずです
学校や先生方と子供の特性や困りごとを共有しておくことで、子供に合った入学準備や対処をしやすくなるのもメリットといえるでしょう。
先生に相談するほどじゃないけど不安なことは、先輩保護者に相談してみるのもおすすめです。



授業参観や保護者会などで知り合った保護者と雑談の中で、ちょっとしたことを相談するようにしています
また、先輩から話を聞くだけでなく、私も支援学校で開催している未就学児向けの保護者向けのイベントに参加して、過去の私と同じように悩んでいた方の疑問や不安に応えるようにしています。
医療機関や療育センターなど学校以外の相談先も作っておく
可能であれば、医療機関や療育センター、放デイなど学校以外の相談先も確保しておくと安心です。
特別支援学校は教育機関であるため、医療や療育的な支援は必ずしも十分に受けられるとは限りません。
発達外来や療育センター、福祉サービスの相談窓口などとつながっておけば、学校生活で困りごとが出てきたとき、専門的な視点でアドバイスを受けられます。



場合によっては、学校や病院などの関係者を集め、子供の特性や学習の進め方について話し合う場も作ってもらえます
私の場合、月に1度、医療機関の療育に通っているのですが、特別支援学校の近くに療育センターがあることもあり、小学部の担任の先生が一度見学に来てくれました。



ST・OTさんと担任の先生で息子について簡単に話し合うことができて、とてもありがたかったです!
SNSで情報収集をしておく
最近ではSNSを通じて、特別支援学校に通う保護者の体験談や工夫を知ることもできます。
もちろん、お住まいの地域や通っている学校によって違いはあるものの、共通する悩みや対処法が見つかる場合もあり、非常に参考になります。



私の場合、持ち物の名前の書き方や連絡帳の書き方などちょっとしたアイデアを参考にすることがあります
ただし、SNSで情報収集をするときには、以下のようなことに注意をしておく必要があります。
- 情報はあくまでも一例であると理解する
- 自分がSNSで相談するときには個人情報を記載しないようにする
- 誤った情報や悪意のある情報もあると理解する
特別支援学校の入学後に意識したこと
息子が少しでも学校で過ごしやすくなるように、入学後も焦りすぎず、以下のようなことを意識しています。
- 忘れ物をしない
- 子供の持ち物に大きく記名する
- 学用品は子供が自分で使えるものを選ぶ
- 学校内では笑顔・挨拶を心がける
- 子供の成長は数ヶ月単位で見守る
- 学校に楽しく通えればよしとする
それぞれ詳しく解説していきます。
忘れ物をしない
特別支援学校では、通常の学習に加えて生活単元学習や調理実習、地域交流など活動の幅が広いため、イレギュラーな持ち物を指定されることがあります。



忘れ物をしてしまうと授業に参加できなかったり、子供が困ってしまったりするので、毎日念入りに確認しています
子供の持ち物に大きく記名する
息子が通う特別支援学校は生徒数が比較的少ないのですが、それでも持ち物被りがあるので、できるだけ大きく記名をするようにしています。



息子は弱視で自分の持ち物を認識しにくいことがあるため、教職員や他の児童が見て息子のものだとわかりやすくすることを意識しています
学用品は子供が自分で使えるものを選ぶ
特別支援学校でも鉛筆やはさみ、のりなどを使用することがありますが、こういった学用品は子供が1人で使えるものを選びましょう。
息子は手先が不器用なので、鉛筆で書いても筆圧が弱くなったり、紙質によってはハサミで上手に切れなかったりすることがあります。
そのため、鉛筆であればいくつかの濃さで試し息子が使いやすいものを選んだり、力を入れなくても切りやすいハサミなどを用意しました。
他には、傘や雨カッパ、エプロンなども自分で脱ぎ着できるものや、片付けられるものを選んでいます。



ネットショップなどで「幼児」「簡単」などのキーワードで検索すると見つけやすくなります!
学校内では笑顔・挨拶を心がける
特別支援学校では先生や保護者との距離が近く、日々のやりとりも多いため、教職員や児童と会ったときには笑顔で挨拶するようにしています。



ちょっとした一言のやり取りでも信頼関係が築け、子供の様子を伝えてもらいやすくなりますし、子供にとって手本を示せるメリットもあるはずです
子供の成長は数ヶ月単位で見守る
入学してすぐは「うちの子だけできていないのでは」「学校のカリキュラムについていけないのでは」と心配でしたが、特別支援学校での成長は一日や一週間で見えるものではありません。
例えば、入学当時には1人ですることが難しかった身支度や挨拶が自然にできるようになっていたり、友達との関わりが少しずつ増えていたり。



焦らず見守る姿勢が、親自身の安心にもつながりました
学校に楽しく通えればよしとする
何よりも意識したのは、学力やスキルよりも、まず学校に楽しく通えることが一番大切という考え方です。
朝起きて「学校に行きたい!」と思えることは、子供にとっても家庭にとっても大きな安心につながるはずです。
幸い、息子は1学期中は行き渋りなどはなく、毎日楽しそうに通ってくれました。
特別支援学校の入学についてよくある質問
最後に、特別支援学校の入学についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 特別支援学校の子供は大学に通えないのですか?
-
結論から言うと、特別支援学校に通っていても、子供の発達や学力の状況によっては大学進学できる可能性があります。
高等部を卒業すれば、高等学校卒業と同等の資格が認められ、大学や専門学校の受験資格を得られるからです。
実際に、特別支援学校から大学に進学する生徒も一定数存在します。
- 特別支援学校と地域の公立小(普通学級)の違いは何ですか?
-
特別支援学校と普通学級の大きな違いは、教育の内容と環境の柔軟さにあります。
地域の小学校(普通学級)は、学習指導要領に沿って全員が同じペースで進むことを基本としています。
一方、特別支援学校では子供一人ひとりの発達や特性に合わせた個別の教育計画が立てられます。
【まとめ】入学後のギャップ解消には事前のリサーチが重要でした
特別支援学校に入学すると、学習内容や学校生活の進め方、家庭との連携の濃さなど、地域の小学校とは違う独自の特徴が見えてきます。
最初は驚きや戸惑いもありますが、子供の特性に合った教育や支援が受けられるのは大きな安心につながるはずです。
障害のある子供が小学校に入学するにあたり、大切なことは子供に合う環境を選ぶこととできるだけ前向きに学校生活を受け止めることだと考えています。



周囲のサポートを活用しながら見守ることで、子供が少しずつ学校に馴染む手助けをしていきましょう
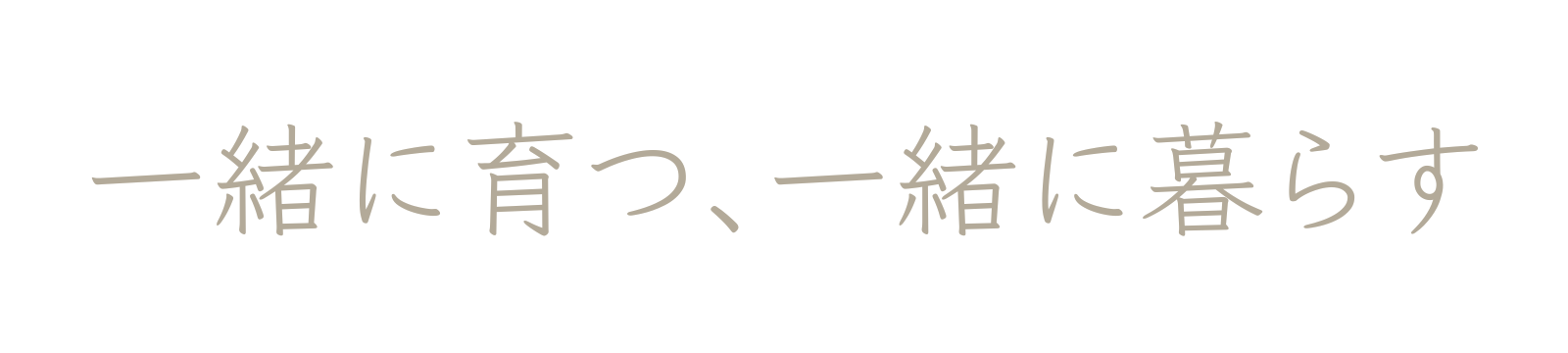




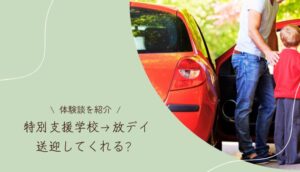

コメント