 お悩み
お悩み子供が特別支援学校に入学したけど、先生とはどんな風に連携していけば良いのかな?



学校生活のことをどこまで教えてもらえるのか、反対に家庭でのことをどこまで話せば良いのか不安……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、特別支援学校の先生と保護者が連携していくコツを紹介します。
- 特別支援学校の先生と保護者はどんな方法で連携するのか
- 特別支援学校の先生と保護者が連携するコツ
特別支援学校や支援学級では、一人ひとりの子供に合った支援を行うために、先生と保護者の連携が欠かせません。
けれど「どうやって先生にお願いすればいい?」「どこまで任せていいの?」と悩むことも多いものです。
本記事では、連絡帳や面談などの基本的なやり取りから、感謝の伝え方や配慮の依頼方法など実際に役立つ連携のコツをまとめました。
特別支援学校の先生と保護者はどんな方法で連携する?
特別支援学校では、一人ひとりの子供の特性に合わせた教育や支援が行われています。
そのため、地域の公立小(普通級)と比較すると、先生と保護者がしっかりと連携し合うことが大切になってきます。
息子は特別支援学校に通っているのですが、私は先生と以下のような方法で連絡を取りあったり連携したりしています。
- 毎日の連絡帳
- 個人面談・授業参観
- その他の学校訪問
それぞれ詳しく解説していきます。
毎日の連絡帳
特別支援学校では、ほとんどの場合、連絡帳を通じたやり取りが行われます。
保育園のように、保護者と先生が連絡帳で毎日やり取りするイメージです。
連絡帳は単なる出欠や体調報告にとどまらず、子供の小さな成長や困りごとを書き留める場所でもあります。



参考程度に先生と私が連絡帳で書く内容を紹介します
- 給食のメニュー、息子が食べた量
- 排泄の記録
- 時間割
- 学校での様子(頑張っていたことや困ったこと)
- その他の連絡事項
- 自宅での様子(何をしたか、機嫌は良かったか)
- 先生が書いてくれた内容への返事、お礼
- 育児相談
- 欠席連絡
息子の担任の先生はマメな性格なので、毎日丁寧に連絡帳を書いてくれるので助かっています。
私も文章を書くことがそれほど苦ではないので、お互い毎日みっちり連絡帳を書きあっています。
個人面談・授業参観
特別支援学校は個人面談の回数も普通級より多い印象です。
息子が通う特別支援学校では、下記のタイミングで個人面談が行われます。
- 1学期始め
- 1学期終わり
- 2学期始め(希望制)
- 2学期終わり
- 3学期始め(希望制)
- 3学期終わり



授業参観は各学期ごとに1回行われています
個人面談では30分程度、先生とお話する機会をもらえるので、普段の様子やこれからの目標などを共有できます。
息子は良くも悪くも、家でも放デイでも学校でも態度や様子が変わらないので、その旨を教共有しています。



個人面談は息子の教室で行われるので、学校の設備などを確認し、視覚支援の方法を勉強させてもらうこともあります
その他の学校訪問時
授業参観や個人面談以外でも学校に訪問したタイミングで、先生と軽く世間話することがあります。



息子は月に1~2回、療育や診察で遅刻するので、遅刻の送迎時に先生と話すことがほとんどです
私は参加していないのですが、PTA活動に参加されている保護者の方は、もっと先生とお会いする機会もあるのだと思います。
先生も、学校訪問時に連絡帳では伝えにくいちょっとしたことや最近頑張っていることを伝えてくれます。



私も連絡帳では言い切れないお礼や診察、療育の様子を伝えるようにしています


特別支援学校の先生と保護者が連携するコツ
障がいのある子供は学習内容や生活習慣が定着しにくいことがあるため、家庭と学校で連携することが非常に重要です。



学校と家庭で意見や対応がバラバラだと、子供も混乱してしまうので……
普段の生活の中で、以下のように意識して先生と保護者が連携していくと良いでしょう。
- 学校・先生に感謝の気持ちを持つ
- 先生の手間・子供の困りごとを減らす方法を考える
- 伝えたいこと・お願いしたいことは「相談」という形を取る
- 放デイや医療機関との連携役を担う
- 保護者と連携したがらない先生には医療機関・放デイ経由で依頼をする
- 提出物の期限厳守や持ち物記名・挨拶など基本的なことを大切にする
- ある程度は学校に任せる意識を持つ
それぞれ詳しく解説していきます。
学校・先生に感謝の気持ちを持つ
まず大前提として、先生に対して「子供を支えてくれてありがとう」という感謝の気持ちを持つことが大切だと思います。
保護者が学校や先生に対して信頼や感謝の気持ちを持てば、子供も同じように思いやすくなるからです。
特別支援学校の先生は、一人ひとりの特性に合わせた支援を行うために多くの準備や配慮をしてくれてします。
お世辞を言う必要や極端にこびる必要はないですが、普段の中で感謝の気持ちを伝えて、協力的な関係を作れるようにしていきましょう。



連絡帳で「ありがとうございます」」と書いたり、面談や学校訪問時に感謝の気持ちを伝える程度で大丈夫です
先生の手間・子供の困りごとを減らす方法を考える
学校や先生との連携を考えるにあたり、先生の手間や子供の困りごとそのものを減らす方法ないかと考えるようにしています。
私の場合、風邪をひいて休みがちになるのも嫌ですし、疲れて機嫌が悪くならないように、子供は早寝早起きさせるように心がけています。
他にも、忘れものをしないようにしたり、持ち物に大きく記名をしたり、息子が好きなことを先生と共有したりと、ちょっとしたことですが意識するようにしています。
伝えたいこと・お願いしたいことは「相談」という形を取る
子供のことでお願いしたいことがある場合には、依頼ではなく、まずは相談という形を取っています。
例えば、息子の場合、利き手と反対側で食器を持って食事をすることが苦手です。
以前、OTで「食器を持たせてからフォークなどを持たせて」とアドバイスをもらったので、学校でもその順番で食事するように依頼しています。



学校側でも食事中の様子を細かく見ていただき、机の高さなども改善していただいています!
放デイや医療機関との連携役を担う
学校との連携だけでなく、放デイや医療機関との連携も保護者が積極的に間に入るように意識しています。
保護者からしたら、放デイと医療機関、学校で連携して諸々良い感じに進めてほしい……と思うですが、個人情報保護の観点で保護者の同意がないと情報共有は難しいようです。
- 「〇〇共有して良いですか?」と各機関や担当者に聞かれてから回答するのではなく、私が共有してしまう
- 放デイのモニタリングや神経内科受診時には学校からの質問、要望はないか先生に聞く
簡単なことですが、普段からやっておくことで学校や先生側からも「何かあったらみんなで協力してやっていけそう」という雰囲気を作れていると思います。
特別支援学校・支援学級で保護者と先生が連携するときによくある質問
最後に、特別支援学校や支援学級で保護者と先生が連携するにあたり、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 保護者が配慮を依頼するときにはどのように先生に伝えれば良いですか?
-
子供の特性に応じた配慮をお願いしたいときは、一方的な要望ではなく「相談」という形で伝えるのが効果的です。
例えば、「家庭では〇〇で落ち着けています。学校でも取り入れられるでしょうか?」と具体例を添えると、先生も受け止めやすくなるはずです。
基本的には先生を信じて親子で先生・学校好き!という気持ちを伝えています
先生との信頼関係は、日々の小さな積み重ねから生まれます。
感謝を伝えたり、提出物の機嫌を守ったり、相談ベースで要望を伝えたりといった基本を意識するだけで、連携はスムーズに進むはずです。
万が一、学校との連携に不安があるのであれば、放デイや医療機関などの関係者を巻き込んでチーム全体で子供の成長に良い働きかけをしていく意識を持つのも良いでしょう。
このブログでは、知的障害+弱視の息子との暮らしについて書いています。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました
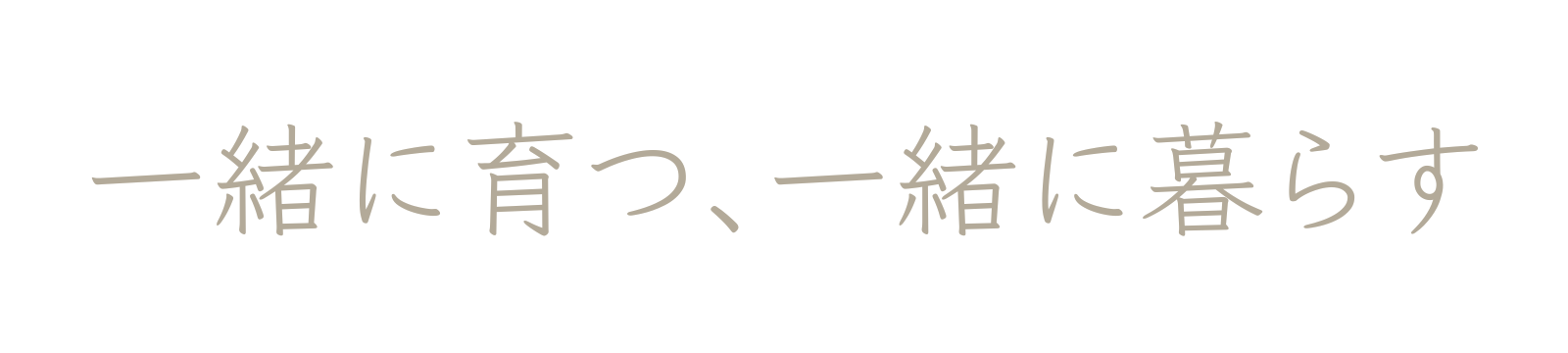




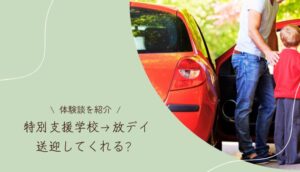

コメント