 お悩み
お悩み子供が特別支援学校に入学するんだけど、入学準備はどんなことをすれば良いのかな?



入学後の生活も想像しにくいし、普通学級と同じように入学準備をするのは難しそう……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、特別支援学校の小学校に入学する際にしておきたい準備を紹介していきます。
- 特別支援学校の小学校入学準備でやって良かったこと
- 特別支援学校の小学校入学準備でやらなくて良かったこと
軽度知的障害+弱視の息子は、2025年4月に特別支援学校に入学しました。
これまで幼稚園に通っており、加配がついていれば何とか園生活を送れていたものの、小学校に入学してやっていけるかどうかや、どんな入学準備をすればよいかはわからず非常に不安でした。



病院や療育の先生、学校関係者に聞いても「入学後に困っても先生はプロだから大丈夫ですよ」しか言ってもらえず……
本記事では、同じように悩んでいる親子に向け、年長後半から無理のない範囲でやってきた入学準備の中でやっておいて良かったものを紹介していきます。
就学相談の流れについては「【体験談】就学相談はいつからいつまで?流れやスケジュールを紹介」の記事で紹介しているので、よろしければ併せてお読みください。


【特別支援学校】小学校の入学準備でやって良かったこと
特別支援学校の小学部の入学準備でやっておいて良かったことは、主に下記の通りです。
- 生活スケジュールを考えておく・練習しておく
- 登下校の道を確認する
- 自分で着替える練習をする
- 服の前後がわかるように印をつけておく
- 学用品を使う練習をする
- 持ち物にとにかく大きく名前を書く
- 放課後等デイサービスを見つけておく
- 困ったときに言語化する練習をする
- 「名前呼び+挨拶」の練習をしておく
- 子供の情報を整理しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
生活スケジュールを考えておく・練習しておく
小学校入学後は幼稚園時代より登校が早くなるので、生活スケジュールを考えておきました。



支援学校・支援学級の場合、付き添い登校が前提となっていることも多く、家族みんなのスケジュールを考えておきました
我が家では、基本的に私が徒歩20分(片道)のスクールバスまで送ると決めたので、朝の流れや仕事に割ける時間を考えておきました。
| 6:30 | 起床・身支度 |
|---|---|
| 7:30 | 登校 |
| 8:20 | 付き添いを終え、私が帰宅 |
| 8:45 | 仕事開始(在宅) |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | 仕事の残りをこなす |
| 14:00 | 終業・片付けなど |
| 14:20 | お迎え |
| 15:30 | 息子と帰宅・お風呂や夕食準備など夕方の家事 |
| 19:00 | 子供たちが就寝・寝かしつけ |
| 19:30 | 私の自由時間 |
息子が放デイに行かない日は、上記のスケジュールで動いています!



仕事が終わらない日は夕方や夜に仕事をすることもあります……
息子は寝るのが早く、寝起きも良いので、生活スケジュールを身につけるのは比較的楽でした。
ただ、幼稚園の登園は9時だったので、朝の自由時間が短くなることに、息子は最初戸惑っているようでした。
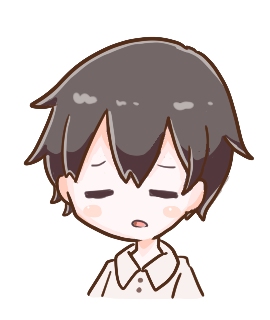
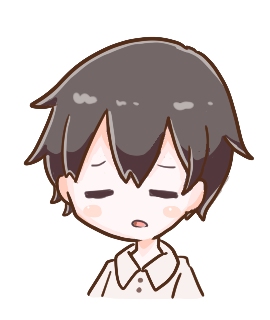
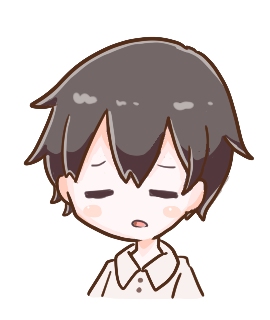
朝ごはんと着替えとチャレンジしたら、もう行く時間……
テレビ観る時間がない……
こんな風に落ち込んでいたので、放課後はテレビの時間が長くなることに目をつぶり、本人の自由に過ごしてもらうようにしています。
また、本人がスケジュール通りに行動できるように、1日のやること+今週の予定をボードを使って管理しています。



ボードは手作りしようと思いましたら、kutuwaのものを購入しました!
お金はかかりましたけど、可愛くて使い勝手もよく最高です!
登下校の道を確認する
特別支援学校はスクールバス通学が多いですが、登下校の道を確認しておきましょう。
地域によってはスクールバスのバス停が遠いこともあるので、どれくらいの時間がかかるかや、どんな交通手段で行くかを確認しておくと安心です。
我が家は、恥ずかしいことに、私が車の運転が苦手+運動不足解消のためにも、バス停まで片道20分の距離を息子と歩いています。



息子も体力がつくので、良いかなと思っています!
また、通う学校によってはスクールバスに乗れる子が限られていたり、年齢制限が設けられていたりすることもあるのでご注意ください。
学校やバス乗車希望者の人数によっては、小学校高学年くらいからスクールバスに乗れなくなる子もいるので、自宅から学校までの登下校についても確認しておくことをおすすめします。
自分で着替える練習をする
特別支援学校の小学部に入学すると、まずは身辺自立から始めることが多いはずです。
発達に偏りのある子や遅れのある子は、身辺自立が身につくのも時間がかかるので、とにかく数をこなすしかありません。
息子も幼稚園では制服→体操服と着替えを練習していましたが、自宅でも私が手伝わず1人で着替える練習をしました。
とはいっても、普段の生活の中で着替えを準備するだけに留め「ママ忙しいから1人で着替えてしててね」「早く着替えたら、その分遊ぶ時間が増えるよ!」と伝えるだけでした。
その他、靴の脱ぎ履きや左右の区別、靴下を履くことなど子供が特別苦手にしている動作があれば、とにかく練習回数を増やして入学後の苦労を減らしてあげましょう。
服の前後がわかるように印をつけておく
息子の場合、服の前後を理解しなかったので、ほとんどすべての服にマークをつけました。


上記のように、シャツの後ろにマークをつけて「ここを持てば着替えられる」と決めてしまいました。
「マークをつけると、いつまでも服の前後がわからないかな」と悩んだのですが、大人になっても悩むようであればそのときに考えようと思い、とにかく今は学校生活をスムーズにすることを重視しています。
ズボンについては、ポケットやボタンなどがなくわかりにくい服のみはマークをつけています。
マークがあれば本人も1人で着替えられると思っているようで新しい服を購入したときには「これもつけてね」と言われます。
学用品を使う練習をする
入学後はどれくらい先生がサポートしてくれるかわからなかったので、学用品を1人で使う練習をしました。
- はさみ
- のり
- 鉛筆
- 消しゴム
上記のように、基本的な学用品の使い方はもちろんですが、準備品として指定されていた穴あけパンチやファイルの使い方も練習しておきました。
ファイルや穴あけパンチは手を挟んだらどうしようと不安だったのですが、一緒に練習することで息子も安心して使えるようになりました。
また、穴あけパンチは息子が使う様子を確認し、見えにくい部分にガイドをつけています。





これも息子が使う姿を確認していないとできなかったことなので、本当に準備していて良かったです!
持ち物にとにかく大きく名前を書く
先生の手間をできるだけ減らすため+本人が自分のものを見つけやすくするために、持ち物には大きく名前を書いておきました。



おしゃれさとか、プライバシーとか二の次です!
名前付けは学用品の場合はお名前シールを使い、布小物系はフェルトでワッペンを作って縫い付けています。



映画やアニメを観ながら毎日少しずつやる!と決めて、楽しみながらできました
後は、学用品を購入するときに息子に何色が良いかや、どんな柄が良いかを聞き、少しでも息子が「これは自分のもの」と覚えられるように工夫しています。
放課後等デイサービスを見つけておく
特別支援学校や支援学級に子供が通う場合、放課後の居場所として放課後等デイサービスを選んでおきましょう。
障害のある子供を対象に、放課後や長期休暇などに訓練・支援を行うための福祉サービス
特別支援学校の場合、学校に併設されている学童なんてありませんし、支援学級だとしても友達トラブルや子供が嫌がるなどの理由で学童を利用できないこともあります。
放デイは普段の放課後だけでなく、長期休暇中の預け先にもなるので、早めに押さえておきましょう。
地域によっては施設に空きがないことも珍しくないので、年長の早い段階で見学・予約をしておくことを強くおすすめします。



息子の場合、児童発達支援(未就学児対象)も行っている放デイを選び、持ち上がり扱いで利用することができています!


困ったときに言語化する練習をする
子供が困ったときについ先回しして支援してしまいがちですが、グッと我慢して、困ったときに自分の言葉で伝える練習をしました。
特別支援学校に通う子供たちは、困ったり嫌なことがあったりしたときに、言語化するのではなく、黙ってしまったり、癇癪を起こしたりしてしまうことも珍しくありません。
息子の場合、癇癪はないものの甘えん坊で困ったときにシクシクと泣いてしまうことが多かったので「泣き終わったら、何に困ったのか伝えて」と言い、泣いていても解決できない環境をあえて作りました。
息子が落ち着き「◯◯がわからなかった」「◯◯が怖い」と伝えてくれたら、言えたことを褒めて、息子の困りごとに対応しています。



新しいことに取り組む際に自分で想像して不安なことを伝えてくれるようになりました
先日も「放デイで動物園に行けるよ、お弁当も持っていけるよ」と伝えたら、少し悩みながら「お弁当を動物に食べられたらどうしたらよいか」聞かれました。
「そんなことで悩むの!?」と驚くことも多いのですが、余裕がある限り、丁寧に息子の不安に向き合うようにしています。
「名前呼び+挨拶」の練習をしておく
特別支援学校の見学・体験をしたときに「名前呼び(◯◯さん、◯◯先生)+挨拶」が徹底されていたので、息子とも練習していました。
息子は軽度知的障害と弱視の重複障害だからか、人の顔と名前を一致させるのが非常に苦手です。
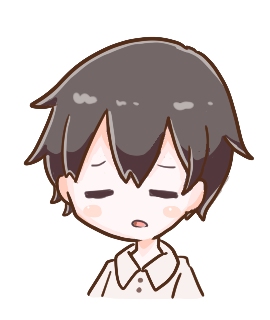
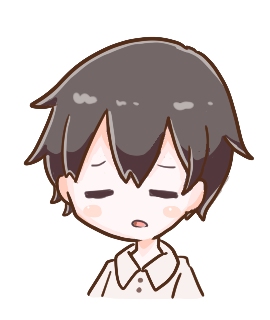
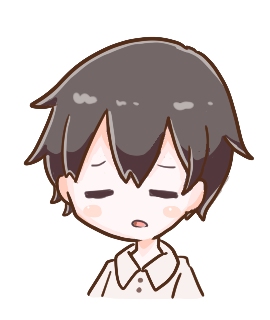
名前がわからないから話しかけられない……
こんな機会も多かったので、入学後に困る機会を減らすためにも、放デイにも協力してもらって練習しています。



放デイはスタッフや利用者が曜日によって異なるため、息子は全然名前を覚えられていなかったのですが、今では少しずつ覚えているようです
特別支援学校に入学後は、担任やクラスの友達以外の方の名前も覚えつつあるので、本当に練習していて良かった!と思います。
子供の情報を整理しておく
特別支援学校に入学するにあたり、とにかく様々な書類を書かなければならないのが大変でした。
住所や家族構成といった基本情報だけでなく、既往歴やかかりつけ医なども書かなければならないので、子供の情報を整理してまとめておくことをおすすめします。



後は、誰に何を話したを忘れがちなので、提出書類はコピーして、控えを自宅で保管するようにしています
息子は眼科や小児神経科など複数科を受診しているので、とにかく私が情報のハブとなって必要な機関に共有できるようにしています。
なお、発達に偏りのある子や遅れのある子が入学するにあたり、サポートブックを作ることも多いのではないでしょうか。
我が家も必要かと思いましたが、確認したところ、問題が発生すれば、関係者全員で面談もできるので不要と言われたので、特に作ってはいません。
病院や療育施設、学校などの距離が離れていて面談などが難しい場合には、サポートブックを作っておくのも良いでしょう。
【特別支援学校】小学校の入学準備でやらなくても良かったこと
「小学校 入学準備」などで検索すると、ほとんどの情報が普通学級に入学する子供を想定しており、特別支援学校や支援学級に入学する子の場合、「こんなに準備できない」と頭がクラクラしてしまいそうになりますよね。
我が家でも、様々な情報に振り回されそうになりましたが、下記の準備はしなくて良かったと感じています。
- ひらがなや数字の詰め込み学習
- 1人で通う練習
それぞれ詳しく解説していきます。
ひらがなや数字の詰め込み学習
息子は普通学級ではなく特別支援学校に入学したため、ひらがなや数字など小学1年生で習う内容の先取り学習は行いませんでした。
年長では「こどもちゃれんじジャンプ」を受講したものの、ひらがな・カタカナの読みは自分の名前程度しかできるようになりませんでした。
「学習させた方が良いかな」と思いつつも「プロである先生が息子に良いやり方を見つけてくれるだろう」と思って、お任せしています。



良い勉強方法が見つかり、宿題なども増えてくれば、家庭学習にも力を入れていきたいです!
とはいえ、年長で「こどもちゃれんじジャンプ」を受講したことで、家庭学習の習慣も身につき、数字などにも慣れてきたので本当に良かったと思います。
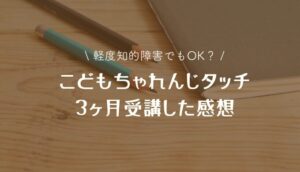
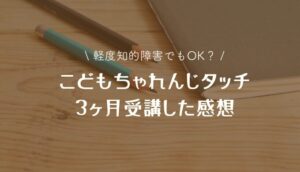
1人で通う練習
息子の進学先は特別支援学校であり、スクールバスも用意されています。



息子の場合、重複障害扱いなので、スクールバスも優先的に乗れるそうです
スクールバスのバス停までは保護者の付き添いが必須なので、息子が1人で歩くことは基本的にありません。
「1人で歩けるかも」なんて息子が思わないように、1人で歩く練習はしていません。
息子が成長し、1人での外出練習が始まったら、家庭でも1人歩きの練習を行おうと思っています。
特別支援学校の小学校入学準備についてよくある質問
最後に、特別支援学校の小学校入学準備についてよくある質問を回答とともに紹介していきます。
- 特別支援学校の入学式はどんな服装をすれば良いですか?
-
基本的には、学校の指示に従うのが良いでしょう。
我が家は、特に指定がなかったので、フォーマル服を着ました!
- 特別支援学校は療育手帳(愛の手帳)がなくても入学できますか?
-
特別支援学校と療育手帳は直接の関係がなく、療育手帳がなくても特別支援学校に入学できます。
とはいえ、特別支援学校の児童・生徒の枠には限りがあるため、療育手帳を取得している子供が優先される可能性はあります。
【まとめ】学校・療育施設と連携しながら入学準備を進めましょう
特別支援学校に入学する場合、事前に就学相談を受けておく必要がありますし、医師による診察も必要です。
無事、入学が決まった後は、入学先の学校や就学相談の担当者、医師などと連携しながら入学準備を進めていくと良いでしょう。
特別支援学校は、良くも悪くも個々の成長や特性に合った教育をしてくれるので、学校や子供によって必要な準備も変わってくるはずです。
この記事が、特別支援学校・支援学級に入学予定であり、不安な親子のためになると幸いです。



ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
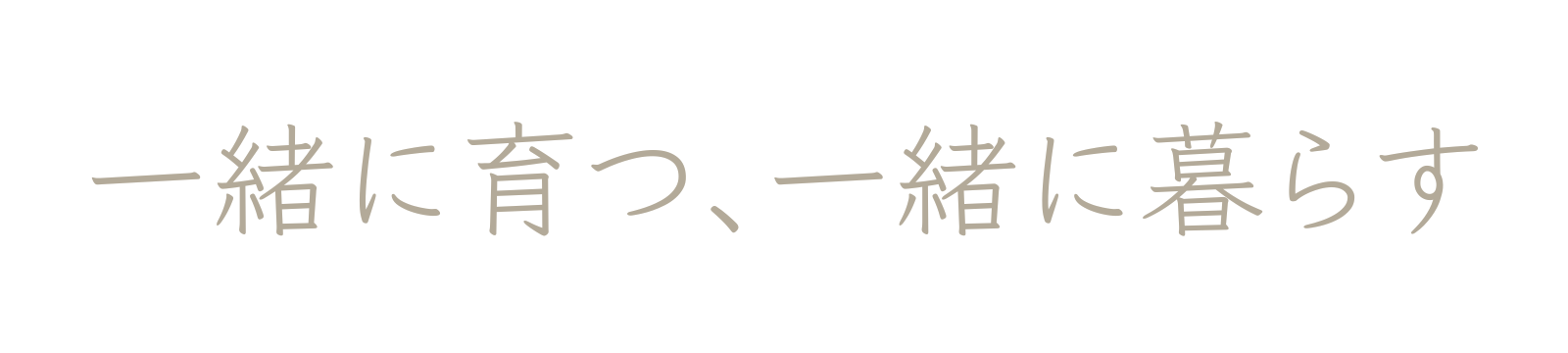
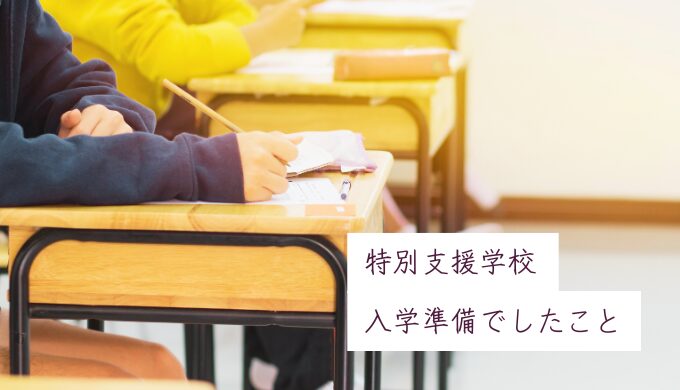



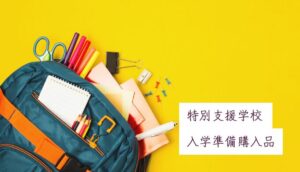
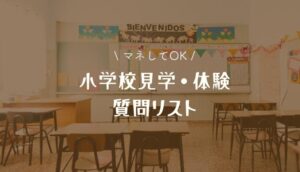

コメント