 お悩み
お悩み年長の息子がひらがなが読めないんだけど、やっぱりまずいかな……



知的障害のある子供は何歳くらいでひらがなが読めるのかな……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向けて、ひらがなが読めない原因や実際に試してみた学習方法を解説します。
- ひらがなが読めるのは何歳くらいなのか
- ひらがなが読めるようになるまでの流れ
- ひらがなが読めないときに考えられる原因
- 知的障害のあるこどものひらがな学習方法
「うちの子、もう年長なのにひらがなが読めない……」
そんな不安を抱える親御さんは少なくありません。
ですが、ひらがなが読めるようになる時期には個人差があり、発達の特性や興味の有無によってペースは様々です。
本記事では、ひらがなが読めるようになるまでの発達の流れや、読めない場合に考えられる原因について実体験をもとに紹介します。
ひらがなが読めるのは何歳くらい?
「ひらがなは小学校で習った気がする」「とはいえ、幼稚園でひらがなを普通に読める子が多いはず」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
一般的には、ひらがなの読みを習得するのは年中から年長頃と言われています。
ただし、本格的にひらがなを学習するのは小学1年生の1学期ですので、幼稚園・保育園の時点でひらがなの読み書きが完璧にできていなくても問題にはなりません。
年長児の約9割がひらがなを読める
一般的に、ひらがなの読みを習得するのは、年中・年長頃と言われています。
文部科学省の調査や幼児教育現場のデータでは、年長児の約9割がひらがなを読めるという結果が出ています。
参考:幼児教育、幼小接続に関する現状について|教育課程企画特別部会
この時期の子供たちの発達には大きな個人差があり、早い子では3歳頃から読み始める一方で、就学前でもまだ読みが定着していない子も少なくありません。
「読めない=遅れている」と一概には言えず、ひらがなが読めない場合、視覚認知や言語理解、記憶の発達ペース、家庭での文字への接触頻度など、複数の要因が関わっていることがほとんどです。



文字への興味がまだ薄い子や、言葉の音に注意を向ける力が発達途上の子供は、自然と習得までに時間がかかることがあります。
また、知的障害や学習障害(LD)などが背景にある場合は、以下のような特徴が見られることもあります。
- 覚えてもすぐ忘れてしまう
- 似た文字を区別できない
- 読むことを嫌がる
ただし、家庭で焦らず、遊びを通して文字と関わる時間を積み重ねることで、少しずつ進歩する子も多くいます。



小学1年生の息子も軽度知的障害+弱視ではあるものの、少しずつひらがなの読める字を増やしています
小学1年生の1学期でひらがなの読み方・書き方を学習する
学校教育のカリキュラムでは、小学1年生の1学期にひらがなの読み書きを集中して学ぶことになっています。
文部科学省の学習指導要領でも、入学直後の国語の授業では「ひらがな46文字の読み書き」を体系的に学ぶよう設計されているからです。
そのため、入学時点で読めない子供がいても、1学期の終わりには多くの子が読み書きできるようになります。
ただし、発達に凹凸がある子供や境界知能の子供の場合、集団授業のペースが速く感じられることもあるでしょう。
そうしたときは、学校の授業や宿題に加え、家庭でも以下のようなサポートをしなければならないことがあります。
- 絵カードやラベルなどで「見てわかる」環境を作る
- 音と文字を一緒に示す(例:「あ」は「あひるの“あ”」)
- 1日1文字など、短時間・少量をコツコツ繰り返す
- 書く前に「読む練習」を優先する
特に、知的障害や学習障害のある子の場合は、「覚えること」よりも「生活の中で使えるようにする」ことを重視する方が、本人の自信にもつながります。



日常生活で、ひらがなの読み書きに触れる機会を増やすことが習得につながります
ひらがなを読めるようになるまでの流れ
ひらがなを読めるようになるまでには、「文字を見て理解する力」だけでなく「音と結びつけて意味をとる力」など、複数の発達が関わっています。
具体的には、以下のような流れで読めるようになることが一般的です。
- 眼球を動かし読む文字に焦点を合わせる
- ひらがなの形を識別する
- ひらがなの音と形をマッチングさせる
それぞれ詳しく解説していきます。
眼球を動かし読む文字に焦点を合わせる
ひらがなを読むための最初の段階は、「目で文字を追う力(視覚の追従)」と「焦点を合わせる力(ピント調節)」です。
大人にとっては当たり前のことですが、小さな子供にとってはこれも発達途中にあるスキルです。



息子のように、視覚障害があると、読む文字に焦点を合わせるのはより難しくなるはずです……
例えば、文字を指で追うことができない場合や、行を飛ばして読んでしまう場合には、眼球運動の発達が安定していない可能性があります。
特に、弱視や斜視など、目の使い方に課題がある子供の場合は、「文字を見ても上手く焦点が合わない」「文字がブレて見える」などの理由で読みにくさを感じることがあります。
視力の問題が疑われる場合は、眼科や視能訓練士によるチェックを受けることも大切です。
ひらがなの形を識別する
次の段階は、「形を見分ける力(視覚認知)」であり、ひらがなの形を見て、それぞれが違う文字であることを理解する力が必要となります。
例えば、ひらがなの中には、「ぬ」と「め」、「は」と「ほ」など似ている文字もいくつかあります。
ひらがなをまだ習得していない子供にとっては、文字の細かい違いを見分けるのは難しいものです。
特に、知的障害や発達障害のある子供では、この「形の識別」が苦手な場合があります。



文字を「記号」として捉える抽象的な力が育ちにくいからです
この段階では、書く練習や読む練習を急ぐよりも、「見てわかる」「触ってわかる」体験を増やすことが効果的です。
息子の場合、以下のような遊びをして、ひらがなを練習しています。
- 文字カードを使って同じ文字を探す「マッチング遊び」
- 粘土やマグネットで文字の形を作る
- お風呂の壁や冷蔵庫に貼って遊ぶ
上記のように、文字を形として親しませていくことで、それぞれの違いに注目できるようになってきます。
ひらがなの音と形をマッチングさせる
最終段階として、「文字の形」と「音」を結びつけていきます。
例えば、「あ」という形を見て「あ」と発音するように、視覚情報と聴覚情報を結びつける力が必要です。
知的障害や発達障害の子供は物事を覚えるのが苦手なこともあるので、少しでも本人にとって意味のある体験と結び付けて覚えさせることが大切です。
単純に「これは『あ』です」と教えても覚えにくいので、「ありの『あ』」「いぬの『い』」など、身近な言葉と一緒に覚える方が、記憶に残りやすくなります。



子供が好きなものやよく使う単語に絡めて、練習していくことをおすすめします!
また、知的障害や発達障害のある子供は、音と文字の対応づけが上手くいかないことや、活舌が悪くそもそも発音が曖昧な場合もあります。
その場合には、以下のような工夫が効果的です。
- 絵と音をセットにしたフラッシュカードを使う
- 音を口に出しながら文字を見る
- 「あ・い・う・え・お」の歌やリズム遊びを取り入れる
活舌が悪い場合や、覚えが悪い場合も決して焦らず、毎日少しずつ取り組んでいくことが重要です。
【注意】単語や文章の理解とひらがなの読みは別問題である
子供がひらがなを読めないとき、「ことばの理解力が低いのでは」と心配する保護者は多いですが、単語や文章の理解力と、ひらがなの読みの力はまったく別のスキルです。
ひらがなを読む力は、目で見た形を音に変換する「デコーディング(読み取り)」の力です。
一方で、単語や文章の意味を理解する力は、語彙力や文法理解力、背景知識などを使って「意味づけ」する力です。
つまり、ひらがなが読めなくても、耳で聞いた言葉の意味はきちんと理解できる子供も多いものです。
他にも、ひらがなは読めても内容が理解できない場合もあります。
娘は恐らく定型発達ですが、ひらがなは覚えたものの、文章を読めない時期が続きました。



「ここ読んで」と言えば音読はできるのに、問題を解けいないことにずっと悩まされていました
とはいえ、娘も成長につれ、自然と絵本を自分で読んだり、文章を読んで問題を解けるようになりました。
ひらがなが読めない場合に考えられる原因
子供がなかなかひらがなを読めるようにならない場合、以下のような原因が考えられます。
- 文字やひらがなに興味がない
- 聴覚性短期記憶が苦手である
- ひらがなの形や文字の違いを認識できない
- 読み書き障害(ディスレキシア)がある
それぞれ詳しく解説していきます。
文字やひらがなに興味がない
発達の早い・遅いにかかわらず、「そもそも文字に興味がない」というケースは非常に多いものです。
ひらがなに触れる機会が少なかったり、遊びや生活の中で文字が登場しない環境だったりすると、自然と関心が薄れます。



上の子は教えないとひらがなを読めなかったのに、下の子は上の子の教材に自然と触れ、早くから読めたなんて話はよく聞きますよね
この場合、まずは「勉強」ではなく「遊び」から文字に親しむことが大切です。
例えば、以下のようなことを子供と一緒に楽しみながらしてみるのもおすすめです。
- 絵本を一緒に読む
- 好きなキャラクターの名前を文字で探す
- 家の中のものにラベルを貼る



とにかく「文字を生活の中で使う」経験を積むことを意識してみましょう
聴覚性短期記憶が苦手である
ひらがなの読みには、聞いた音を一時的に覚えておく力(聴覚性短期記憶)が深く関わります。
例えば、「か・き・く・け・こ」と言われたときに、一時的にその音を記憶しておき、次の瞬間に文字と照合する力が必要です。
この作業が苦手な子供は、音を聞いたそばから忘れてしまうため、何度も同じ文字を見ているのになかなか覚えられません。



この場合は、繰り返しの練習をすることはもちろんですが、歌やリズム、身体を使った学習も有効です
ひらがなの形や文字の違いを認識できない
「ぬ」と「め」や「さ」と「き」など、似た形の文字を見分けにくい場合、視覚認知(形を正しく識別する力)に課題があるかもしれません。
文字をただ模様として見ている状態では、どれがどの文字か区別するのが難しくなってしまいます。
このような場合は、書いたり見たりして覚えるだけではなく、実際に文字の形を触ってみるのも有効です。
STさんに言われた方法ですが、ひも状の粘土を用意し、文字を作ってみるのもおすすめだそうです。



視覚認知の課題は訓練で改善することも多いので、焦らずゆっくり取り組みましょう
読み書き障害(ディスレキシア)がある
ひらがなを熱心に練習しているにも関わらず、以下のような状況が続く場合には、読み書き障害(ディスレキシあ)の可能性があります。
- 何度練習しても覚えられない
- 読もうとすると極端に疲れる
- 読むスピードが上がらない
ディスレキシアは知的能力とは関係なく、文字を音に変換する脳の処理に特性がある状態です。



診断や支援を受けることで、無理のない学び方を見つけられます
また、子供がディスレキシアかどうかは、保護者や支援者が自分たちで判断するのではなく、医療機関などで専門医に診断してもらうことが大切です。
万が一、子供がディスレキシアだとわかった場合も、悲観しすぎる必要はなく、子供に合ったペースで、負担の少ない方法を探していきましょう。
定型発達の子と知的障害のある子ではどんな違いがある?
同じ「ひらがなを読む」という課題に向き合うときでも、定型発達の子と知的障害のある子では、学び方や理解のスピード、得意・不得意のポイントに明確な違いがあります。
本章では、定型発達の娘と知的障害の息子を育てた経験を持つ私が、それぞれのひらがなの定着の流れや学習方法について解説します。
定型発達の娘の場合
定型発達の娘がひらがなを読み始めたのは、年中の終わりごろでした。
文字に興味を持ち始めたというより、受講していたこどもチャレンジでひらがなを学習し始めたタイミングで自然と読めるようになりました。
読み聞かせはしていましたし、たまに子供とお手紙ごっこなどで遊ぶことはありましたが、それ以外は特に勉強をさせていませんでした。
ただ、娘は女の子ということもあり、幼稚園時代から周りとの子供の差をよく気にしているようでした。
娘は早生まれなこともあり、「他の子は読めるようになっている」「他の子供は友達同士で手紙交換している」と思って、文字を読みたい!と思ったのもあるかと思います。
娘の場合、ひらがなを読むのはそれほど苦戦しませんでしたが、以下のような学習では苦戦していました。
- カタカナの読み(なかなか読めるようになりませんでした)
- 文字を読んで意図を理解する(1人で問題を読んで解くのには時間がかかりました)


知的障害+弱視の息子の場合
一方で、軽度知的障害+弱視の息子は、定型発達の娘とはまったく違うペースで学習を進めています。
まず、年中から年長にかけては視力の伸びも悪く、発達の遅れが理由で視力検査も難しかった状況があります。
そのため、保護者である私もかかりつけ医も幼稚園の先生も「息子がどこまで見えているのか」をわかっていない状態でした。
私も息子がどこまで成長するかが全く読めなかったので、ひらがなの学習も無理にさせていませんでした。



自分の名前だけは、小学校入学前に読めるようにしておきました
息子の場合、小学1年生の秋の段階で、ひらがなを3分の1から半分程度読むことができます。
今は特別支援学校と月に1度のST、私とやっている自宅学習でひらがなを根気強く学習中です。
知的障害+弱視の息子にひらがなを定着させるためにやったこと
息子とは年長の秋・冬頃から無理のない範囲でひらがな学習を進め、小学校入学時点では自分の名前、小1の秋時点ではひらがなの3分の1から半分程度読めるようになっています。
入学後の個人面談で担任の先生から「息子くんが自分の名前を読めるようになるまで、本当にお母さん頑張られたと思います……!」と言ってもらえたこともあり、息子に合ったひらがな学習ができているのでは?と思っています。
具体的には、以下のような学習を日替わりで本人が楽しめることを第一に進めています。
| 頻度 | 内容 |
|---|---|
| 毎日 | 絵本の読み聞かせ(暗唱+親による読み聞かせ) |
| 日替わり | 積み木を使った単語学習ひらがなを書く練習 |
| スキマ時間・外出中 | 同じ音の単語を考えるゲーム単語の文字数を数えるゲームしりとり |
それぞれ詳しく紹介していきます。
絵本の読み聞かせはできるだけ毎日する
絵本の読み聞かせは、できるだけ毎日するようにしています。
短い絵本を1~3冊ほどなので、そんなに時間はかけていません。
絵本の読み聞かせは文字学習というより、語彙力を少しでも増やすため、音で言葉を理解できるようにするためにしています。
息子も読み聞かせを喜び、赤ちゃんのときから何度も読んでいる絵本は文字を読めないながらも暗唱してくれます。



ひらがな学習が完了に近づいたら、これまで読んであげていた絵本を少しずつ自分で読む練習を取り入れる予定です
文字を指でなぞらせてみる
息子は視覚障害があるので、視覚だけでなく触覚も活用して、ひらがな学習をしています。



あまり私に余裕がなく準備できていないときには、大きめに書かれたひらがなの文字を一緒に指でなぞっています
反対に、ちょっと息子にやる気があるときや、私に余裕があるときには、細長くした粘土や毛糸、モールなどでひらがなの形を作り触って確認しています。
先日、息子がモールで遊んでいて「見て、ママ!『く』」と言って、自分1人で「く」の形を作ってくれたので、ある程度の効果は出ているはずです。
自分の名前や好きなものなどの文字の並びを覚えさせる
STさんからのアドバイスで1文字1音ずつ学習するより、単語で覚えさせてと言われたので、息子になじみのある単語を中心に文字の並び方を覚える練習をしています。
- 息子の名前
- くるま
- いちご
- あさ・ひる・よる
- 先生の名前
- 家族の名前
こんな感じで息子がやってみたいと言った単語を中心に学習を進めています。
単語の並びを覚えさせる練習としては、こんな感じで進めることがほとんどです。
- 私が文字を並べる
- 一文字ずつ一緒に読む
- 初見の文字は形を確認する
- バラバラにして息子に正しく並び替えさせる
同じ単語を1週間に2~3単語繰り返し、定着したら次に進むようにしています。
文字に興味が出てきたら書く練習や同じ音の単語を考えるゲームを取り入れる
小1の夏から秋にかけて、息子がひらがなに興味を持つようになったので、書く練習や同じ音の単語を考えるゲームを取り入れています。
書く練習は大きめのマスのノートを用意して、私が見本を書き、その下に息子が書くことをしています。
同じ音の単語を考えるゲームは「『く』がつく言葉を考えてみよう」「『し』から始まるもの順番に言ってみよう」などと遊び感覚でしています。



息子が疲れているときには、ゲームだけで済ませることもあります
他には、単語の文字数を数えるゲームとして「5文字の言葉なんだ?」「知っている言葉でできるだけ長い言葉教えて!」などと楽しみながら勉強しています



最近の息子は「しりとり」もできるようになりました
子供がひらがなを読めずに悩んでいるときによくある質問
最後に、子供がひらがなを読めるようにならず、悩んでいるときによくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 5歳児でひらがなが読めなくても心配ないでしょうか?
-
5歳になってもひらがなが読めないと、「うちの子だけ遅いのでは」と不安になる親御さんは多いものです。
しかし、結論から言うと、5歳でひらがなが読めないこと自体は決して珍しいことではありません。
発達のスピードには大きな個人差があります。年中〜年長の間にひらがなを読み始める子もいれば、小学校に入ってから急に読めるようになる子もいます。
- ADHDが書く字の特徴はどんなものがありますか?
-
ADHD(注意欠如・多動症)の子供は、集中力や手先のコントロールに波があるため、書く文字にも独特の特徴が現れることがあります。
個人差は大きいですが、一般的には以下のような傾向が見られます。- 文字の大きさや間隔がバラバラになる
- 行やマス目から文字がはみ出す
- 書き順や向きを間違えやすい
- 集中力が切れると書き崩れる
- 書くこと自体に強い疲労を感じる
- ひらがなを読めない子供への支援にはどんなものがありますか?
-
ひらがなが読めない場合、学校や地域、専門機関にはさまざまな支援があります。
まず、小学校入学前なら「発達支援センター」や「療育センター」に相談するのが一般的です。
発達検査(田中ビネー、WISCなど)を通して、どの力が伸びていてどの力が苦手なのかを明らかにし、適切な練習法を提案してもらえます。入学後であれば、特別支援学級(支援級)や通級指導教室を利用できる場合もあります。
支援級では少人数で、1人ひとりの理解度に合わせた指導を受けられます。
【まとめ】専門家のアドバイス+家庭学習が上手くいきました
ひらがなを読めるようになるには、目で見て、音を聞き、形を識別し、意味を理解するという多くの発達段階を踏まなければなりません。
大人は何気なくこなしていることですが、子供にとっては非常に難しい場合もあります。
子供がひらがなをなかなか読めるようにならないとしても、焦りすぎず、子供の得意な感覚に合わせたアプローチを取り入れることが大切です。
たとえペースがゆっくりでも、「読めた!」という成功体験を積み重ねることで、子供は少しずつ自信をつけていきます。
発達の遅れや偏りに不安がある場合には、親だけで抱え込むのではなく、かかりつけ医や療育センター、発達支援センターに相談してみるのもおすすめです。
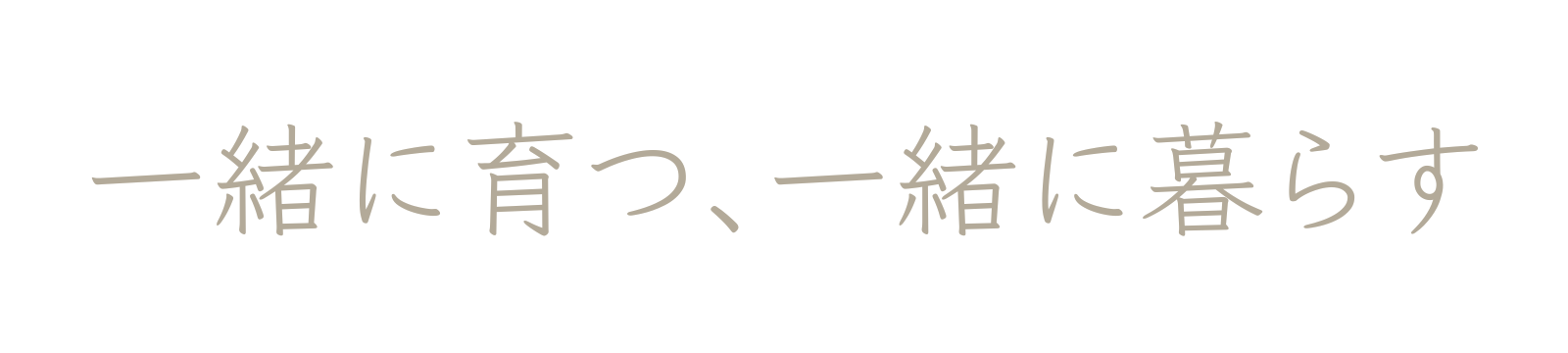
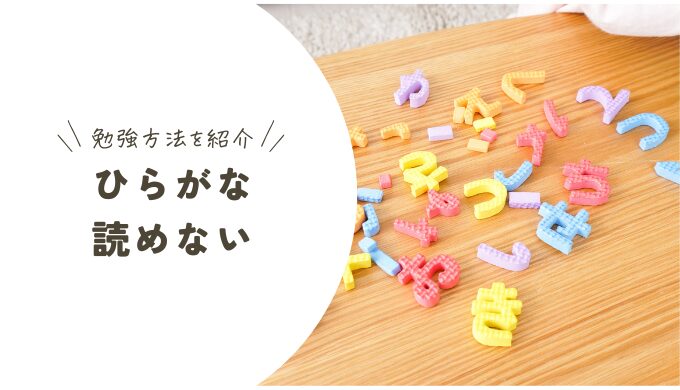
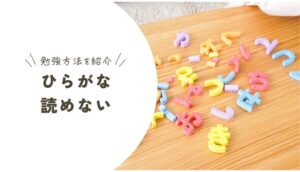
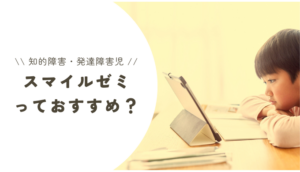

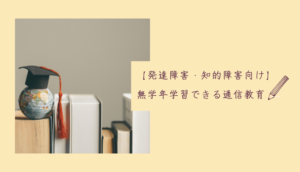

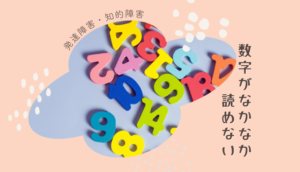
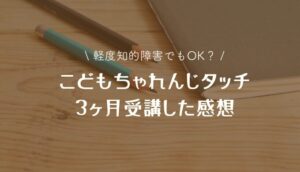
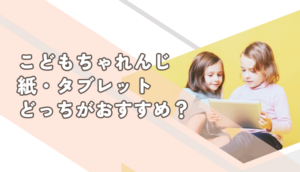
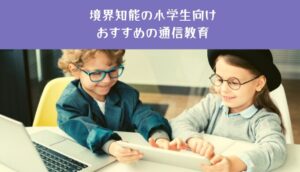
コメント