 お悩み
お悩み知的障害の子供には通信教育は向いていないのかな?



少しでも学習を定着させるために、通信教育を受講しようかな……
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、知的障害の子供には通信教育は向いているのかを解説します。
- 知的障害の子供に通信教育は向いてないのか
- 知的障害の子供におすすめの通信教育
知的障害のある子供の場合、通信教育の受講は難しいと思うかもしれません。
しかし、近年ではタブレット型の通信教育も充実しているため、子供の特性に合った教材を見つけることも可能です。
実際に、軽度知的障害+弱視の息子も学年を遅らせて、こどもちゃれんじタッチ(年長向け)を受講しています。
本記事では、我が家の体験談をもとに、知的障害の子供に通信教育は向いているのかを解説していきます。
【体験談】知的障害の子供に通信教育は向いてない?
我が家の息子は軽度知的障害と弱視があり、これまでにもいくつかの通信教育を試してきました。
結論から言うと、知的障害のある子供や支援級・支援学校似通っている子供は通信教育の種類によっては向いていない場合もあります。
本章では、息子が通信教育を受講したときに感じたことをもとに知的障害の子供に通信教育が向いているかを解説します。
学年相当の教材を受講するのは難しいかもしれない
知的障害のある子供の場合、年齢=学年ではなく「発達段階」に合わせて考えることが大切です。
息子も当初は「とりあえず学年通りの年長コース」と思って教材を申し込みましたが、内容が理解できず、文字や数の概念があいまいなまま進んでしまいました。



学習中は親の見守りが常に必要であり、子供が勝手に勉強する環境は作れないと感じました
一般的な通信教育は、進度が自動的に上がっていくため、つまずきを見逃しやすいのも難点といえるでしょう。
発達年齢相当の教材であれば問題を解ける場合もある
一方で、発達年齢に合わせて内容を下げた教材を選ぶと、「できた!」という成功体験を積めることもあります。
息子の場合、2025年時点で小1になりましたが、まだ年長向けの通信教育を受講しています。
無理なく楽しめる内容に変えたことで、自分から「今日もやる!」と取り組むようになり、1日分のワークに集中して取り組めるようになりました。



教材の対象年齢にこだわらず、子供が理解できるレベルから始めることが何より大切だと思います
我が家の場合、学年を遅らせてでも子供に合う通信教育を選んだことで、数やひらがなが定着しやすくなったと感じます。
紙教材よりもタブレット教材の方が集中しやすい
息子の場合、問題を自分で読めないので、紙教材よりタブレットが向いていました。



息子は弱視なので、動画や音声などで伝えてくれるタブレット教材の方がわかりやすいようです
とはいえ、タブレット教材では運筆練習の機会が少ないので、余裕があるときに幼児向けの紙のワークに取り組んでいます。



支援学校では、運筆練習に力を入れてくれているので助かっています
息子が受講しているこどもチャレンジたっちは、科学や芸術分野の動画教材もあるので、息子も楽しんで何度も観たり遊んだりしています。
子供1人で学習を進めることは難しい
通信教育のキャッチコピーでよくあるのが「子供が自分で進められる学習方法」「親が家事をしている間に子供が1人で勉強できる」といったものですが、知的障害のある子供が受講する場合、親の見守りが必要です。
タブレットの操作や問題の意図を読み取ることが難しい場合があるので、親が側で見守りサポートをしなければなりません。
我が家は、朝の登校前にこどもチャレンジたっちをやらせているのですが、化粧をしている私やヒゲを剃っている夫が隣で代わる代わる息子を見守っています。



「登校前に機嫌を損ねてほしくはない」「でも勉強はしてほしい」と考えているので、もう朝はドキドキです
タブレット教材は自動丸付け機能がついており、親の見守り不要なイメージがありますが、子供も慣れてくると理解していなくても答えを適当にタップし次の問題に進みます。
何度か不正解の音がしたら、子供の様子を気にかけ、必要に応じでアドバイスやヒントを与えるのが我が家の見守り方です。
【体験談】知的障害の息子は学年を遅らせてこどもちゃれんじタッチを受講中
軽度知的障害+弱視の息子は、2025年時点で小1ですが、年長向けのこどもちゃれんじタッチを受講しています。



昨年も年長向け教材を受講していたので、今年で2年目です
学年を遅らせることになりましたが、2年目の今年の方が明らかに学習内容を理解した上で問題に解答しているように感じます。
本章では、息子にこどもちゃれんじタッチをやらせてみた感想を紹介します。
年長のタイミングで「こどもちゃれんじタッチ」を受講開始(学年相当)
年長になったタイミングで、とりあえず学年相当のこどもちゃれんじタッチをやらせることにしました。
字が読めず、弱視もある息子の場合、紙教材のこどもチャレンジではなく、タブレット教材のタッチ一択でした。
学年相当の教材を選んだのは、あまりに難しいならその時点で遅らせれば良いと思ったのと、普通学級に進むことになった場合の予習をしたかったからです。
息子はタブレット学習こそ受け入れていたものの、ひらがな・カタカナの問題や時計の問題などはまるで理解していませんでした。



一方、プログラミング関係のゲームや芸術分野のアクティビティ、科学関係の動画は学年相当のものを理解し楽しんでいました
1年生になるタイミングでもう一度「こどもちゃれんじタッチ」を受講(1学年遅らせ)
息子が小学校に入学する際に、もう1年こどもチャレンジたっちを受講することを決めました。
1年遅らせた理由は、息子が特別支援学校に通うため教科書準拠の教材にこだわらなくて良いことと、息子がまだまだ年長向け教材でも理解が及んでいない部分が多かったからです。
結果として、遅らせたのは大正解で、息子も意欲的に取り組み分かる問題も増えてきました。
我が家にとって、学年を遅らせて通信教育を受講したのは正解だったのですが、学年を遅らせる際には以下のようなデメリットもあるので慎重に判断しましょう。
- 子供が学年を遅らせたことに気付き、やる気をなくしてしまう
- 学年変更の際に手続きをしなければならない
例えば、こどもチャレンジたっちの場合、秋以降は新1年生向けの広告や動画がバンバン流れます。
なぜか息子は楽しそうに観ているのですが「もう僕1年生なのに」と広告に不信感を持つ子もいるはずです。
他には、我が家みたいに学年通りの受講をしていた方が後から遅らせようとすると、一旦解約扱いとなり新規契約が必要な場合もあります。
こどもちゃれんじタッチはタブレットのみ返却交換が必要でした。
一方、スマイルゼミは受講前に学年変更の手続きについて確認したら、解約・新規契約となるので変更のたびにタブレット端末代がかかると言われました……。
知的障害の子供におすすめの通信教育
知的障害の子供が通信教育を受講する場合、慎重に教材を選ばなければなりません。
子供の通信教育といっても、学校の教科書内容に準拠したものから受験対策用のハイレベル教材まで様々なものがあるからです。
知的障害の子供が通信教育を受講するのであれば、以下のような基礎レベルからしっかりフォローしてもらえるものがおすすめです。
それぞれ詳しく解説していきます。
天神
- 幼児から中学生まで幅広い年代に対応
- 教材の種類によっては「無学年方式」で学習できる
- 専用のタブレットが不要
- 買い切り型で継続費用がかからない
天神は、境界知能や発達障害、グレーゾーンの子供たち向けに作られたICT学習教材です。
専用端末を購入する必要はなく、家庭にあるパソコンを使ってすぐに学習を始められる点が特長です。



幼児版・中学生版についてはパソコンだけでなく、タブレットからの受講も可能です
また、一般的な通信教育のように毎月教材が届く形式ではなく、「1教科・1学年ごとに購入する買い切り型」のシステムを採用しています。
そのため、購入した教材・学年によっては無学年で進められるため、苦手分野はさかのぼってしっかり定着させることができます。
得意な教科に関しては先取り学習にも対応しており、積極的に進められるお子さんなら大きな自信につながるはずです。
一方で注意点として、天神の価格は公式サイトに掲載されておらず、費用については資料請求でもらえる冊子に記載されています。



そのため、他の教材と比較しづらい点や気軽に検討しにくいという点はデメリットといえるでしょう
| 対象年齢 | ・幼児 ・小学生 ・中学生 |
|---|---|
| 教材の種類 | パソコン |
| 価格 | 無料で請求できる資料にて価格を確認できる |
| 専用タブレットの要否 | 不要 |
| 教科書準拠 | 〇 |
| 教材レベル | 教科書レベルをしっかり学習できる |
| 無学年学習 | 〇 ※受講科目・学年による |
| 解約金・違約金 | 不要 ※買い切り型の講座のため |
すらら
- 学習継続率は驚きの 89.1%
- 小学生〜高校生まで、どの学年でも「無学年学習」が可能
- 学校や学習塾など教育現場でも幅広く導入されている
すららは、不登校の子供や発達障害がある子供の学習支援を目的に開発された教材でもあり、すららでの学習が出席扱いとして認められたケースも多数あります。
すららが境界知能や発達障害、グレーゾーンの子どもに相性が良いといわれる理由は次の通りです。
- 一歩ずつ進められる「スモールステップ型」の学習設計
- AIと専門知識を持つ「すららコーチ」が作るオーダーメイドの学習計画
- タブレット学習ならではの、両手を使ったインタラクティブな操作
- 音声・動画を組み合わせ、「見る・聞く・話す・書く」をバランスよく学べる
このような特徴が、ワーキングメモリー(短期記憶)に不安がある子供でも理解を積み上げやすい仕組みにつながっています。
子供自身の理解度に合わせて、無理なく戻り学習ができるから、確実に「わかる」を積み重ねられます。
すららで学習することで、以下のような好循環ができれば、学校の授業に追いつきやすくなるでしょう。
- 「できた!」という成功体験が得られる
- 「次もやってみよう」という前向きな気持ちが生まれる
- 取り組むたびにまた「今回もできた!」が積み上がる



勉強への苦手意識を少しずつほどき、自信を育てていく教材として、とても相性が良いサービスといえます
| 対象年齢 | ・小学生 ・中学生 ・高校生 |
|---|---|
| 教材の種類 | タブレット・PC |
| 価格 | 小学生4教科コース:8,228円/月 ※上記の料金は4ヶ月継続コースを利用した場合の1ヶ月あたりの料金 ※上記とは別に入会金11,000円がかかる |
| 専用タブレットの要否 | 不要 |
| 教科書準拠 | △ ※対応リストがあるので保護者が合わせる必要がある |
| 教材レベル | 教科書レベルをしっかり学べる |
| 無学年学習 | 〇 ※受講したコースによって学習できる学年の範囲が異なる |
| 解約金・違約金 | 4ヶ月継続コースを利用した場合、4ヶ月未満で退会すると解約金がかかる 1ヶ月目:572円 2ヶ月目:1,144円 3ヶ月目:1,716円 ※上記の契約解除料金は4教科コースを選択した場合 |
こどもちゃれんじタッチ・チャレンジタッチ
- 小学生だけでなく、幼稚園(年中・年長)から中学生まで幅広く利用できる
- 専用タブレットは半年以上継続すれば端末代が無料
- 漢字と計算は「無学年方式」で本人のレベルに合わせて学習可能
チャレンジタッチは、ベネッセグループが展開する「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材であり、未就学児向けの「こどもちゃれんじタッチ」も提供されています。



なお、進研ゼミでは紙教材での受講も選べます
こどもちゃれんじタッチやチャレンジタッチは、これまで培ってきた進研ゼミのノウハウや強みをタブレット教材で提供している点が特徴です。
私自身も学生時代は高校生まで進研ゼミを受講し、娘も受講させていますが、紙教材しか考えておりませんでした。
しかし、息子のような発達に特性のある子供や遅れのある子供には、タブレット教材がぴったりでした。
境界知能や発達障害、グレーゾーンのある子供の場合、問題文を読むことや鉛筆で答えを書くこと自体が負担になることもあります。
そのような場合、「運筆の練習」と「内容理解・演習」を切り分けて、段階を踏んで進めるスモールステップが理想的です。
その点からも、タブレット型教材は非常に相性が良いといえます。
チャレンジタッチには長年の進研ゼミのノウハウが活かされており、学校の教科書に合わせて学習できるのが大きな特徴です。
- 学校の予習・復習として取り組める
- 必要なだけ繰り返し練習できる
- 漢字・計算は無学年で、得意・苦手に合わせて進められる
このように、子供が無理なく教科書レベルをしっかり理解するための仕組みが整っています。
また、タブレット教材にありがちな「端末代が高い」という悩みも、チャレンジタッチなら半年以上継続すればタブレット代が無料になるため、費用面でも始めやすい教材です。
| 対象年齢 | ・年中・年長 ・小学生 ・中学生 ※高校生は紙教材+スマホ学習 |
|---|---|
| 教材の種類 | タブレット ※紙教材の「チャレンジ」もあり |
| 価格 | 小学1年生:3,250円/月 小学2年生:3,490円/月 小学3年生:4,460円/月 小学4年生:4,980円/月 小学5年生:5,980円/月 小学6年生:6,370円/月 ※上記の料金は12ヶ月先払いをした場合の1ヶ月あたりの料金 |
| 専用タブレットの要否 | 必要 |
| 教科書準拠 | 〇 |
| 教材レベル | 教科書レベルから応用レベルまで対応 |
| 無学年学習 | 〇 ※漢字・計算のみ |
| 解約金・違約金 | 不要 ※6ヶ月未満で退会した場合、専用タブレット代8,300円が発生 |
スマイルゼミ
- 国語・算数は無学年方式で学習可能
- 年中・年長の幼児から高校生まで幅広く対応
- 2週間の無料お試しができる
スマイルゼミは、ATOKの開発やワープロソフト「一太郎」を手がけた株式会社ジャストシステムが提供するタブレット型通信教育です。
教科書に準拠したカリキュラムのため、学校の進度に合わせた学習ができ、授業の予習・復習にも非常に使いやすい設計になっています。
スマイルゼミならではの魅力としては、以下のようなものがあります。
- 音声による読み上げ
- 動画やアニメーションでの丁寧な解説
- 自動採点機能
- マイキャラを育てる楽しみ要素
上記のように、タブレット学習の強みをしっかり活かした仕組みが強みです。
さらに、専用タブレットとカリキュラムを2週間無料で試せるため、お子様との相性を事前にチェックできるのも大きなメリットです。



タブレット学習そのものが合うかどうかも、スマイルゼミの無料体験で気軽に確かめられます
| 対象年齢 | ・幼児 ・小学生 ・中学生 ・高校生 |
|---|---|
| 教材の種類 | タブレット |
| 価格 | 小学1年生:3,828円/月 小学2年生:3,520円/月 小学3年生:4,180円/月 小学4年生:4,840円/月 小学5年生:5,720円/月 小学6年生:6,270円/月 ※上記の料金は12ヶ月先払いをした場合の1ヶ月あたりの料金 ※標準クラス・オプションはつけない場合の料金 ※上記とは別に専用タブレット代10,978円がかかる |
| 専用タブレットの要否 | 必要 |
| 教科書準拠 | 〇 |
| 教材レベル | 教科書レベルから応用レベルまで対応 |
| 無学年学習 | 〇 ※国語・算数のみ |
| 解約金・違約金 | 不要 ※6ヶ月未満で退会した場合、専用タブレット代32,802円がかかる ※6ヶ月以上12ヶ月未満で退会した場合、専用タブレット代7,678円がかかる |
スタディサプリ
- 14日間の無料体験がある
- 小学講座を登録すれば、すべての映像授業が見放題
- アバター育成機能があり、学習習慣づくりにも活用できる
スタディサプリは、小学1年生〜高校3年生までの授業動画が見放題の通信教育サービスです。
学年に関係なく定額で利用できるため、高学年になって苦手科目を復習したい場合にも重宝します。
動画を見るだけでなく、学習内容を理解しているかを確認できるドリルもタブレットで解けるようになっています。



自動採点+解説動画つきなので、子どもが1人で学習を進めやすいのも魅力です
ただし、スタディサプリは非常にコスパの良い教材である一方、サポート機能に関しては少し物足りなさがあります。
- 学習状況を保護者へ知らせる「まなレポ」
- 学習でもらえるコインでキャラクターを育てる「サプモン」
上記のような機能はあるものの、AIや専門スタッフが学習計画を作成してくれる仕組みはありません。
そのため、勉強の進め方を決めるのは親、もしくは子供自身が担う必要があります。



親が計画を立てるのは手間ですし、その通りに子供が取り組んでくれるかも悩ましいところですよね
| 対象年齢 | ・幼児 ・小学生 ・中学生 ・高校生 ※幼児は小学生向け講座を受講できる |
|---|---|
| 教材の種類 | スマホ・タブレット |
| 価格 | 1,815円 ※上記の料金は12ヶ月先払いをした場合の1ヶ月あたりの料金 |
| 専用タブレットの要否 | 不要 |
| 教科書準拠 | △ ※対応リストのみ用意されている |
| 教材レベル | 教科書レベルから応用レベルまで学べる |
| 無学年学習 | 〇 |
| 解約金・違約金 | 不要 |
知的障害の子供の通信教育についてよくある質問
最後に、知的障害の子供の通信教育について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 知的障害の方が苦手なことは何ですか?
-
知的障害のある子供は、理解のスピードや記憶の定着に時間がかかる傾向があります。
特に、抽象的な表現や、指示が複数ある課題を苦手に感じる子供もいます。
また、ワーキングメモリ(作業記憶)が弱い傾向があるため、「聞いたことを覚えながら考える」「順番に手順を追って作業する」といった課題が難しくなりがちです。
- 発達障害の子供はチャレンジタッチとスマイルゼミのどちらがおすすめですか?
-
「チャレンジタッチ」と「スマイルゼミ」はどちらも人気の通信教育ですが、発達障害や知的障害のある子供にとっては向き・不向きがあります。
チャレンジタッチは、キャラクターの声かけや動画解説が豊富で、ゲーム感覚で学べるのが特徴です。
飽きやすい子供や、音声で指示を理解するのが得意な子供には特に向いています。一方のスマイルゼミは、画面がシンプルで落ち着いており、余計な演出が少ないのが特徴です。
刺激に敏感な子にとっては、こちらの方が合う場合もあります。
また、スマイルゼミは筆圧感知のあるペンで「書く」動作を重視しているため、文字練習をしたい子に向いています。 - 知的障害の子供にタブレット学習はおすすめですか?
-
知的障害のある子供には、タブレット学習は非常に相性が良いケースが多々あります。
タップや音声など、五感を使った学びができるので、紙教材よりも楽しく学びやすくなるからです。
また、音声による説明や正解のフィードバックが即時に得られるため、「自分で理解できた」という達成感を感じやすいのも魅力です。
【まとめ】2年目のチャレンジたっちで家庭学習は定着しました
知的障害のある子供だからといって通信教育を受講できないといったことはありません。
しかし、教材の種類によっては1人で学習を進めることが難しいですし、必要に応じて学年を遅らせたり、無学年学習を選択したりする工夫が必要です。
一方で、通信教育が子供の特性や現時点の能力にマッチすれば、自分のペースで学習内容を定着させやすくなります。
我が家も今後、受講する教材の種類や学年を調整しつつ、子供に合った通信教育を受講し続ける予定です。
このブログで紹介した知的障害の子供におすすめの通信教育は、以下の通りです。
いずれも無料体験や資料請求が可能ですので、気になったものは問い合わせてみることをおすすめします。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました
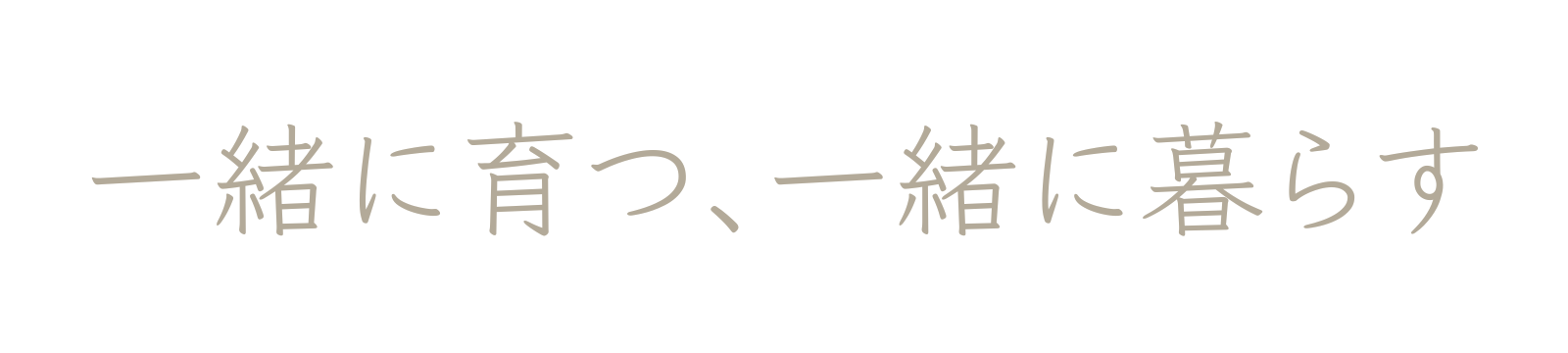
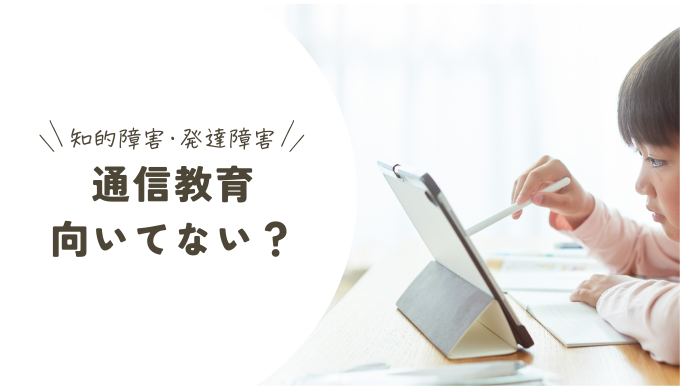
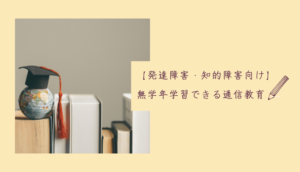
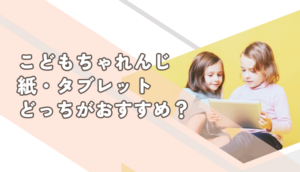
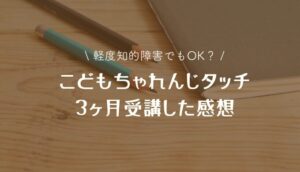

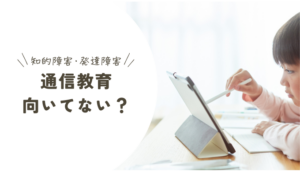
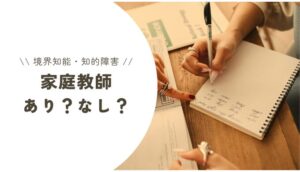
コメント