 お悩み
お悩み子供が軽度知的障害と診断されたんだけど、どんな風に勉強を教えたら良いのかな……



市販のドリルを活用しているけど、全然身につかなくて辛い
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、知的障害の子供は学習に遅れが発生するのか解説します。
- 軽度知的障害の子供は定型発達の子供と同じように学習を進めて良いのか
- 軽度知的障害の子供の学習の進め方
- 【体験談】軽度知的障害+弱視の息子と試したひらがな・数字の学習方法
軽度知的障害のある子供は、定型発達の子供と比べて学習の進み方に個人差があり「なかなかひらがなが覚えられない」「数が数えられない」など、日々の学びの中で不安を感じる場面も多いのではないでしょうか。
私の息子も、軽度知的障害に加え弱視があり、読み書きや数字の学習を進めるにあたり、様々な工夫をしています。
本記事では、軽度知的障害に見られる学習の特性や、効果的な学習の進め方を解説します。
軽度知的障害とは?
軽度知的障害とは、知的発達の遅れがあるものの、日常生活にある程度の適応ができる障害のことを指します。



IQ(知能指数)の目安では50~70程度とされ、支援や環境が整えば自立した生活も可能とされています
軽度知的障害と診断された子供の場合、小学校入学後に読み書きや計算といった学習が始まると、理解に時間がかかったり、抽象的な内容の理解が難しかったりする傾向があります。
とはいえ、軽度知的障害の子供=学習は難しいと考えるのではなく、本人のペースや特性に合った方法で学びを積み重ねていくことが大切です。



私の息子も軽度知的障害+弱視なので、子供に合った学習方法を日々模索中です
軽度知的障害は定型発達と同じ学習方法では遅れやすい
軽度知的障害のある子供に対して、定型発達の子と同じ教科書・同じペースで学習を進めると、どうしてもついていけなかったり、「わからないまま終わってしまったりとなりがちです。
これは、処理速度の遅さや抽象的な言葉の理解が難しいこと、指示を一度にたくさん理解するのが苦手といった特性が影響しているためです。



例えば、算数の文章題を解くときを考えてみましょう
定型発達の子供であれば、文章を読むだけで登場人物の関係や数の増減などを自然に理解し、適切な式を立てられます。
一方で、軽度知的障害の子供は「誰が何をしているのか」「何を聞かれているのか」といった内容を読み取ることに時間がかかったり、混乱してしまったりすることがあります。



問題を読む→式を立てる→計算するといった工程を自分で進められないこともあるでしょう
また、集中力やワーキングメモリが弱い子にとっては黙って机に向かってノートを取るといった一般的な学習スタイルに対応しにくい場合もあります。
軽度知的障害の子供は、自分に合った方法で、繰り返し学習していくことが何より大切です。
【軽度知的障害向け】学習の進め方
軽度知的障害のある子供の学習において大切なことは、その子に合った方法で、焦らず根気よく進めていくことです。
具体的には、以下のような方法を試してみることをおすすめします。
- 繰り返し何度も学習する
- 今やるべきことだけを説明する
- スモールステップに分ける
- 絵や写真などを活用する
- アプリやタブレット学習なども活用する
- 普通学級であれば合理的配慮を依頼する
- 学習のゴールを見直す
- 生活と結びつけて教える
それぞれ詳しく解説していきます。
繰り返し何度も学習する
知的障害のある子供の場合、定型発達の子供より繰り返し学習することが大切です。



知的障害があると、どうしても新しい知識やスキルが一度では定着しにくい場合があるからです
一度できるようになったことや覚えたことでも、日が経つと忘れてしまう場合があるため、日常的に何度も確認し、定着を図りましょう。
例えば、時計の読み方を学んでいる場合は、毎朝「今何時?」と聞いてみたり、「15時になったらおやつ」と時間と行動をセットにして繰り返したりすることで、定着しやすくなります。
今やるべきことだけを説明する
軽度知的障害のある子供と学習する場合には、一度に説明するのではなく、今やるべきことだけを説明するようにしましょう。
知的障害のある子供は、たくさんの情報を一度に処理するのが苦手な子も多いからです。



指示はシンプルに、「短く」「具体的に」伝ましょう
スモールステップに分ける
定型発達の子供にも言えることですが、課題や学習に取り組む場合には、スモールステップに分けることを意識しましょう。
スモールステップに分けることで、今やるべきことに集中しやすく、達成感も得やすくなります。
例えば、読解問題に取り組む場合は、「解いてみて」とだけ伝えるのではなく、以下のように細かく取り組んでいく必要があります。
- 登場人物の名前を見つける
- 何が起こったかを一言で説明する
- 質問に合った答えを選ぶ
絵や写真などを活用する
軽度知的障害の子供が学習をする場合には、絵や写真など視覚的な情報を取り入れるようにしましょう。



抽象的な概念や言葉の理解が難しい場合もあるからです
また、絵や写真などを活用して学習する場合には、車や動物など本人が好きなものを取り入れるのもおすすめです。
アプリやタブレット学習なども活用する
本人の特性や発達段階にもよりますが、アプリやタブレット学習なども取り入れていきましょう。
アプリやタブレット学習であれば、ゲーム感覚で学べますし、繰り返し学習もしやすいので軽度知的障害の子供にも合うでしょう。



タブレット学習は、視覚と音を使ってわかりやすく説明してくれる点もメリットといえるでしょう
普通学級であれば合理的配慮を依頼する
軽度知的障害のある子供が普通学級に通っている場合、学校側に合理的配慮をお願いすることで、学習のしやすさが大きく変わることがあります。
合理的配慮とは、障害のある子供が他の子供と同じように教育を受けられるようにするために、個別に調整を加えることであり、以下のような配慮が考えられます。
- 授業中に口頭での指示だけでなく、板書やメモで視覚的にも伝える
- テストの時間を延長してもらう、問題数を減らす
- プリントのフォントを大きくしたり、内容を簡潔にする
- グループ学習ではなく個別で取り組める時間を設けてもらう
ただし、合理的配慮は親から学校に対して依頼する必要がありますし、どこまで対応してくれるかはケースバイケースです。



学校との連携を取りながら、その子にとって最適な学習環境を整えていきましょう
学習のゴールを見直す
知的障害のあるお子さんの場合、一般的な学年目標にこだわりすぎると、親も子供も苦しくなってしまうことがあります。
「同じ年齢の子はこれくらいできているのに」「小学校では2年生で九九を覚えるのに」と焦ってしまいがちですが、大切なのはその子のペースで確実に学習内容を定着させていくことです。
例えば、九九の丸暗記が難しい場合でも、「2×3は6」のように、生活に結びついた範囲で繰り返し学ぶことで実用的な計算力を身につけられることもあるでしょう。



学力の目標を「学年基準」に合わせるのではなく、子供の今と将来に必要な力に置き換えることで、学びやすくなり達成感も得やすくなります
生活と結びつけて教える
知的障害のある子供にとって、抽象的な学びよりも生活の中で実際に使うことと結びつけて学習した方が定着しやすい傾向があります。



知的障害のある子供は抽象的なことを理解するのが難しい場合もあるので、できるだけ身近なところから学習を始めましょう
例えば、以下のような工夫をしてみることをおすすめします。
- 「7時に起きる」「15時におやつ」など、実生活のスケジュールと連動させて時計の読み方を教える
- 実際に買い物を体験して、お金の勉強や計算の練習をする
- 文章を書く練習をする際に、一言日記を書かせてみる
【体験談】軽度知的障害+弱視の息子のひらがな学習方法
本章では、軽度知的障害+弱視の息子が行っているひらがなの学習方法を紹介していきます。
2025年時点、息子は小1ですが、まだまだひらがなの読み書きは難しく、定着するのに時間がかかりそうです。
STや学校の先生と相談して、以下のようなポイントを押さえて学習を少しずつ進めています。
- 単語の塊で覚えさせる
- 1音1文字を普段の生活の中で意識させる
- 書く練習と読む練習は分けて行う
それぞれ詳しく紹介していきます。
単語の塊で覚えさせる
ひらがなを1文字ずつ教える方法は王道ですが、息子の場合は資力が低く文字の区別が付きにくいことや、ワーキングメモリーが低いため、単語の塊として覚えさせるようにSTさんからアドバイスをもらいました。
- 自分の名前
- 家族の名前
- くるま、いちごなど自分の好きなもの
上記のような単語のマッチングから始めていくと、徐々に1文字ずつでも読めるようになってきました。



今では「くるまの【く】」などのように、知っている単語で使っている文字も認識しています
1音1文字を普段の生活の中で意識させる
単語のマッチングを行うとともに、会話の中で1音1文字を意識する機会をできるだけ増やしました。
スクールバスのバス停までは徒歩20分ほどあるので、息子が飽きない範囲で「く」がつくものを考えたり、知っている単語を1音ずつ分解して考えたりをしていました。
なお、1音1文字を意識させる際には、最初の文字が重要となってきます。
ただ、ご家庭で丁寧な言葉で話していると、最初の文字が何でも「お」になりやすいので、注意してとSTさんからは教えてもらいました。
実際、「さかな」という単語を分解して考えるときに、息子は何度も「おさかな」と言ってしまい中々定着しにくかったことがあります。
知的障害のある子供は、「さかな」と「おさかな」のように1文字違っただけで理解できなくなってしまうことがあるので、家庭や療育、学校などで使う言葉を統一することも大切だと感じました。
書く練習と読む練習は分けて行う
定型発達の子供の場合、ひらがなの読みと書きを一緒に練習してしまうことがほとんどです。
しかし、知的障害のある子にとっては難易度が高いので、読むと書くを分けて学習することを強くおすすめします。
- ひらがなの区別がつきにくく、読むだけで疲れ切ってしまう
- 手先が不器用な子供も多く、書くのに苦手意識を持っている子も多い
息子もSTでは、字の形を理解することや、読むことだけに集中して学習しています。



鉛筆の持ち方や運筆練習については、迷路や運筆用のワークなどを使っています
特に、息子の場合、弱視もあるので、知的な遅れがない子供でも点字器やタイピングで文字を書いている子を目にする機会も多く、書くことについてはそれほど焦っていません。



本人なりにできるところまで学習していけるように、今は苦手意識を作らないように工夫する日々です
【体験談】軽度知的障害+弱視の息子のひらがな学習方法
数字についてはひらがなより数が少ないこともあり、息子も小学校入学前に1~10についての理解は何とかできていました。
息子に数や数字について教えたときには、以下の流れを意識しました。
- 1対1対応を教える
- 数える練習をする
- 数と数字を対応させる
それぞれ詳しく解説していきます。
1対1対応を教える
まず最初に取り組んだのが「1対1対応」であり、主に幼児向けのワークを使って学習しました。
こどもちゃれんじのワークなどだと、しまじろうたち1人ずつに帽子のシールを貼ってあげる課題などが用意されています。
息子の場合、机上課題だけでは馴染みにくいかもと思ったので、ままごとなどで遊びながら「1人1個配って」と練習することもありました。
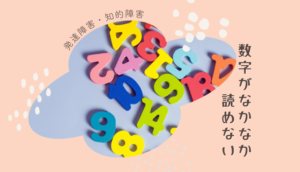
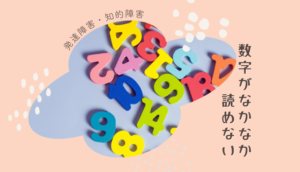
数える練習をする
1対1対応の練習と並行して、数える練習もしていました。
とはいえ、最初のうちは数えることはせず、とにかく1から10を言えるようにしました。
- 10秒数えたらお風呂出よう
- 10秒数えたら〇〇まで走ろう



こんな風に、声に出して数える機会をできるだけ増やしました
そして、1から10を自分で言えるようになってきた頃に、数える練習を本格的に行いました。
- おはじきが何個あるか数えて
- 今日のおやつはチョコレート2つ食べて良いよ
- お菓子を買うから2つ選んで良いよ
数える練習をするときにも、ワークだけでなく、日常で数に触れる機会をできるだけ増やしました。



やはり息子の場合、ワークよりも日常生活で数える方が成功しやすかったです
息子は弱視もあり視野が狭いので数える際には、私が対象を指さし、息子にカウントしてもらうなど、息子が一度にやるべきことをできるだけ減らす工夫もしていました。



視力の問題もあるため、実際に触れるものを数えた方が学びやすかったのだと思います
数と数字を対応させる
最後に取り組んだのが「数」と「数字」の結びつけです。



これは定型発達の育児では、意識していなかった部分なので、盲点でした……
学習内容が定着しにくいから、息子の場合、数えることができても、数に合った数字を選ぶ問題がどうしてもできず、親子で苦労していました。
「書かれているリンゴの数を答えてね」なんて、簡単な問題でも、息子にとっては以下のようにスモールステップに分けなければなりません。
- りんごを漏れなく数える(指と目、声がずれることがある)
- 数えた数を覚えておく
- その数に合った数字を探す
数と数字のマッチングについては、100円ショップで購入した数字のパズルを使っていました。
- 「おはじきを◯個ください」と私が言う
- 息子が言われた数のおはじきと、指定された数字のパズルを取り出して渡す
上記のように、ままごとやお店屋さんごっこを何度か繰り返しているうちに、1から10までの数字を身につけられました。
軽度知的障害の学習遅れについてよくある質問
最後に、軽度知的障害の学習遅れについて、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 知的障害の方は運動面も遅れがありますか?
-
知的障害のある子供は、運動面でも発達の遅れが見られる場合があります。
走ったり、球技をしたりといった身体を大きく使う動きが苦手な場合もありますし、書くことやハサミを使うことなど指先の細かい動きが苦手な場合もあります。
- 知的障害の方に見られる特徴は何ですか?
-
知的障害の現れ方は子供によって異なりますが、軽度知的障害のある子供は、一般的には以下のような傾向が見られます。
- 言葉の理解や表現がゆっくり
- 記憶の定着に時間がかかる
- 抽象的な概念の理解が難しい
- 集中力や注意のコントロールが苦手
- 自尊心が傷つきやすい
子供に合った方法・ペースで学習を進めていきましょう
軽度知的障害のある子供は、学習において「理解に時間がかかる」「忘れやすい」「抽象的なことが苦手」などの特性がある一方で、丁寧なサポートと繰り返しの学びを通じて、確実に力をつけていくことも可能です。
重要なことは、定型発達の子供の学習方法に囚われすぎず、本人に合った方法を見つけて、焦らずゆっくりと学習の土台を築いていくことです。
生活の中で学べる工夫や合理的配慮の活用も効果的ですし、何より「できた!」「わかった!」という小さな成功体験が、子供の自信につながります。



一人ひとりのペースを大切に、前向きに学びを支えていきましょう!
私も息子に合った学習方法を日々探していければと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
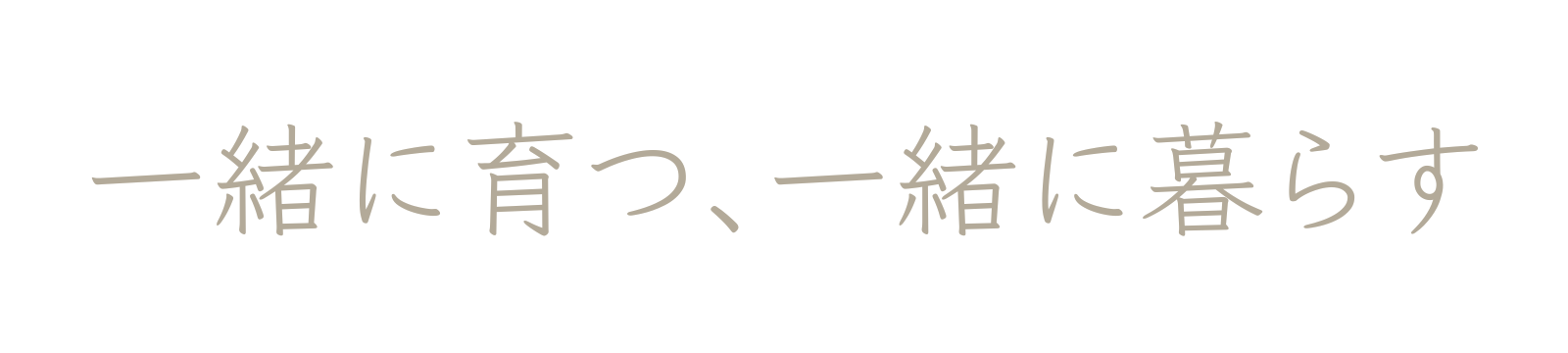



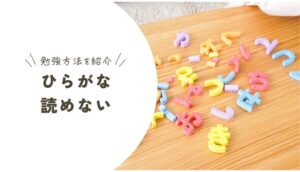
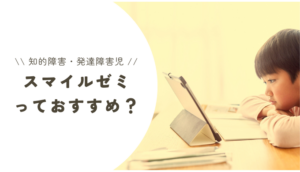
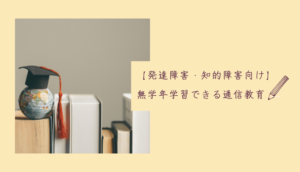

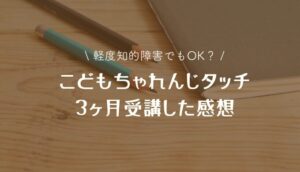
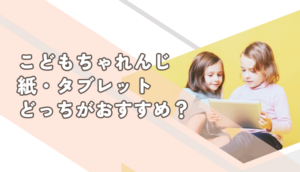
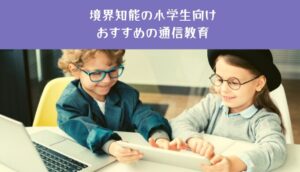
コメント