 お悩み
お悩み子供が発達障害で放課後等デイサービスに通っています
費用は医療費控除の対象になるのかな?



残念ながら、児童発達支援や放課後等デイサービスの費用は原則として医療費控除の対象になりません
本記事では、障害児が通う児童発達支援や放課後等デイサービスに払った費用は医療費控除の対象になるのか詳しく解説していきます。
医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税および住民税から医療費の一部を控除できる制度です。
医療費には通院代や入院費用などが含まれますが、児童発達支援や放課後等デイサービスの費用は原則として医療費控除の対象になりません。
本記事では、医療費控除とは何か、児童発達支援や放課後等デイサービスの費用が医療費控除の対象になる例外的なケースを紹介します。
- 医療費控除とは何か
- 児発や放デイの費用は医療費控除の対象になるか
- 障害児育児にかかる医療費や療育費用を抑える方法
医療費控除とは
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税および住民税の一部を控除する制度です。
具体的には、下記の金額のうちいずれか低い金額を超えた場合、医療費控除の対象となります。
- 総所得金額等の5%
- 10万円



年間を通して支払った医療費が高額の場合、医療費控除をすれば所得税の還付を受けられる可能性がありますよ!
【原則】児童発達支援・放課後等デイサービス費用は医療費控除の対象外
障害児が通う児童発達支援や放課後等デイサービスは、原則として医療費控除の対象外です。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育は、教育や福祉に該当するため医療行為として認められていないからです。
一方で、喀痰吸引や注入など医療行為を児発や放デイで行ってもらった場合は、医療費控除の対象になります。
次の章で、児発や放デイ費用が医療費控除の対象になるケースを詳しく見ていきましょう。
【例外】児童発達支援・放課後等デイサービス費用が医療費控除の対象となるケース
例外として、児童発達支援や放課後等デイサービスの費用が医療費控除の対象となるケースもあります。
喀痰吸引や注入など医療行為に該当する費用に限り、児童発達支援や放課後等デイサービスの費用も医療費控除可能です。
ただし、医療型以外の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用した場合、喀痰吸引や注入にいくらかかったか計算することは困難です。
そのため、児童発達支援や放課後等デイサービスの医療費控除対象額については、下記のように決められています。
| 種類 | 医療費控除の対象条件 | 医療費控除の対象金額 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 介護福祉士などによる喀痰吸引などの対価のみ | 自己負担額 |
| 医療型児童発達支援 | 条件なし | 自己負担額×10% |
| 放課後等デイサービス | 介護福祉士などによる喀痰吸引などの対価のみ | 自己負担額の10% |
| 保育所等訪問支援 | すべて対象外 | 対象外 |
| 医療型障がい児入所支援 | 条件なし | 自己負担額 |
| 福祉型障がい児入所支援 | 介護福祉士などによる喀痰吸引などの対価のみ | 自己負担額の10% |



児童発達支援や放課後等デイサービスの種類によって、医療費控除の対象額が異なるのでご注意ください
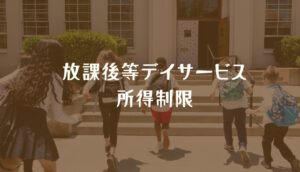
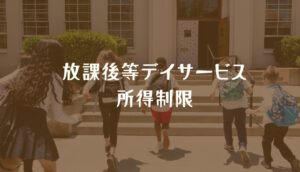
障害児育児にかかる医療費や療育費用を抑える方法
障害児育児をしていると通院も多く、児童発達支援や放課後等デイサービスに通わせ費用がかかることもあるでしょう。



子供のためとはいえ、生活費が圧迫されて辛いとも考えてしまいます……
障害児育児にかかる医療費や療育費用を抑える方法は、主に下記の通りです。
- 対象となる医療費が10万円を超えたら医療費控除をする
- 児発や放課後等デイサービスの所得制限を確認しておく
- 障害児が受けられる支援を漏れなく利用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
対象となる医療費が10万円を超えたら医療費控除をする
年間の医療費が10万円を超える場合、医療費控除を利用すれば、所得税および住民税の負担を軽減できます。
医療費控除の対象となるのは、医療機関への支払いや薬局で購入した薬、病院へに交通費などです。
本記事で解説したように、児童発達支援や放課後等デイサービスの費用は原則として医療費控除の対象外なのでご注意ください。
また、医療費控除を適用するには勤務先の年末調整では対応できないので、確定申告をしなければなりません。



領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります
児発や放課後等デイサービスの所得制限を確認しておく
児童発達支援や放課後等デイサービスには、所得に応じて利用料が軽減される制度があります。
児童発達支援や放課後等デイサービスの負担額の上限は、下記の通りです。
| 区分 | 利用負担額(月額)の上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 区市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 区市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |



自治体によっては、上記に加え所得制限を撤廃している、児童発達支援のみ無料などと決めている場合もあります
パートやアルバイト、フリーランスなど働く時間を調整しやすい仕事をしているのであれば、世帯年収を所得制限ギリギリにして児童発達支援や放課後等デイサービスの月ごとの負担額上限を4,600円にするのも手でしょう。
障害児が受けられる支援を漏れなく利用する
障害児やその家族が利用できる支援制度や助成金は、多岐にわたるので漏れなく活用しましょう。
例えば、障害の程度によっては特別児童扶養手当が支給される場合もあります。
基本的に障害者向けの手当など福祉を利用する際には、自分で情報を取得して申請しなければなりません。



役所の方から「〇〇の制度に該当しますよ、申請すればお金を受け取れますよ」と丁寧に教えてくれることはないと思っておきましょう
子供に障害があるとわかり障害受容に時間がかかる、本人の困り事解消のために行動するので精一杯になりがちですが、利用できる福祉はできるだけ早く確認しておくことをおすすめします。


在宅ワークを始めてスキマ時間にお金を稼ぐのもおすすめ
障害児育児をしていて外で働くことは難しい、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用していてお金がかかることが悩みであれば、在宅ワークを始めてみるのもおすすめです。
WebライティングやWebデザイン、オンライン秘書などの在宅ワークであれば、自宅で作業できるので通勤は不要、スキマ時間にコツコツと作業できます。



子供の体調不良や行き渋り、通院などで欠勤することもないので、ストレスの少ない状態で働けます
私も第一子妊娠中からWebライターとして働いており、子供が急性脳症で入院してからは何度も「Webライターで良かった」「これからも自宅で働きたい」と思ってきました。
在宅ワークはWeb系のスキルやスケジュール管理能力、営業力などが必要であり、問題が起きてもすべて自分で対処しなければなりません。
それでも、自分のペースで少しずつできることを増やしていけば、それに応じて収入も上がっていくはずです。
障害児の医療費控除についてのよくある質問
最後に、障害児の医療費控除についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 医療費控除と障害者控除は併用できる?
-
医療費控除と障害者控除は併用可能です。
ただし、医療費控除もしくは障害者控除を適用した結果、所得が0円になってしまえばそれ以上控除するものがなくなるため、節税効果が得られなくなります。 - 障害児のおむつ代は医療費控除の対象になりますか?
-
障害児が使用しているおむつ代に対して医療費控除を適用するには「おむつ使用証明書」か「おむつ使用認定書」などを発行してもらう必要があります。
おむつ使用証明書やおむつ使用認定書を発行してもらっていない場合は、医療費控除できないのでご注意ください。
医療費控除の対象は細かく決まっているので注意ましょう
年間を通じてかかった医療費が10万円を超えるのであれば、医療費控除を行えば所得税や住民税の負担を軽減可能です。
ただし、児童発達支援や放課後等デイサービスにかかった費用は原則として、医療費控除の対象にならないのでご注意ください。
ただし、医療的ケア児などが注入などの医療行為を児童発達支援や放課後等デイサービスで行った場合は、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象になるかは、子供が通っている通所施設や入所施設の種類によっても異なるので、施設を選ぶ際には確認しておくことが大切です。
この記事を読んだ人が1人でも多く、自分に合う方法で節税、節約をし、家族と楽しい日々を過ごせることを願っています。
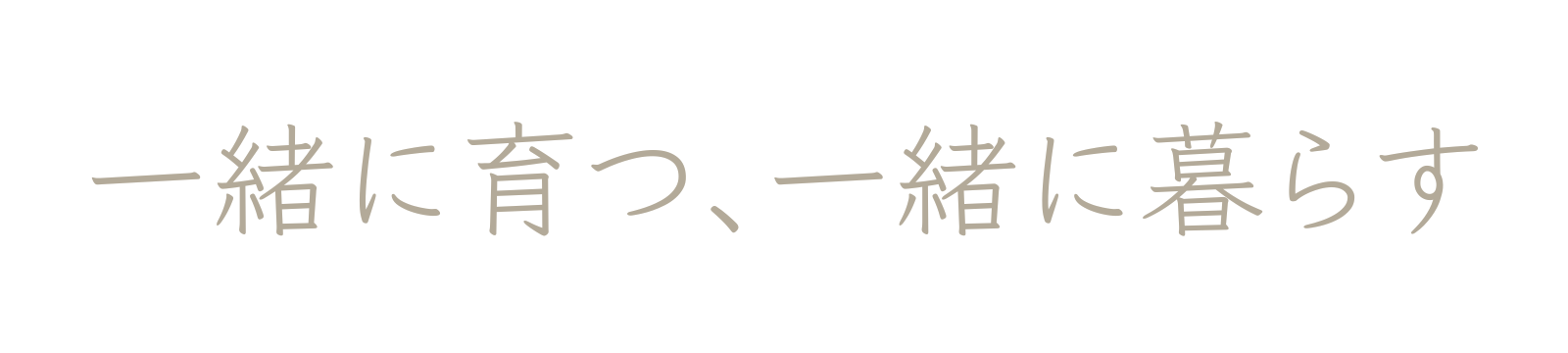
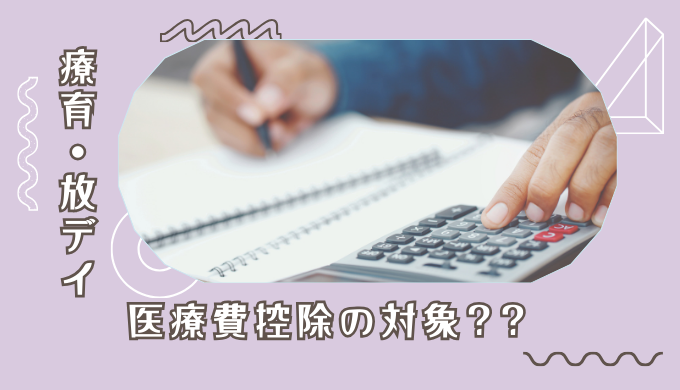
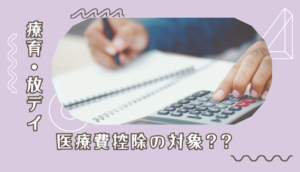


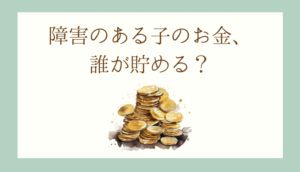
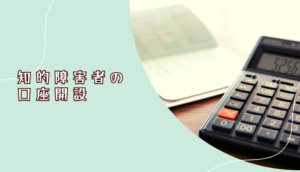


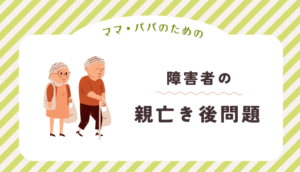
コメント